【空華学轍とは】
空華学轍といわれるものは、明教院僧鎔師(1723~1783)が、号を空華といい、学塾を空華廬といったので、その学轍を空華学轍といったのである。その弟子には柔遠(1742~1798)道穏(1741~1813)の二師があり、柔遠師は常に越中に住していたが、道穏師は多く近畿に住しており、その弟子の性海(越中の生まれ)に至って学説が展開したので、その弟子、善譲などの学派を境空華とも称し、越中を中心にして展開したものを越中空華といっているが、学説としては大筋において異なるものではないようである。もちろん学者によって多少の学説の左右はあるが、それは学者の個性によるもので、その基礎的なものにおいては、まったく同じ傾向のものである。
 この学轍には、柔遠・道穏の後には、行照、性海、善譲、鮮妙などの諸学匠が配出し、道穏の弟子月珠は師説とはやや趣を異にする学説を説いて、豊前学派とはいっているが、この学轍からの分派というべきである。しかも、明治の初年までは、西本願寺の宗学においては、主流的な役割をしてきたものである。
この学轍には、柔遠・道穏の後には、行照、性海、善譲、鮮妙などの諸学匠が配出し、道穏の弟子月珠は師説とはやや趣を異にする学説を説いて、豊前学派とはいっているが、この学轍からの分派というべきである。しかも、明治の初年までは、西本願寺の宗学においては、主流的な役割をしてきたものである。
この学轍の特色ともいうべきものの一つは、おそらく柔遠師によってはじまったもののようであるが越中で学寮を開き、子弟を教育しても、各々の学匠は、自分の弟子としないで、僧鎔の墓に参らせて空華の学弟子といったようである。だから、学者が学塾を開いても、その学寮の学生であるという印に木札に「丸に花」という焼きばんのあるものを用いていた。それは私の子供の時、祖父の印順の仏母寮の学生が、托鉢に出るとき、仏母の学生であることの証明として用いた木札が本堂の裏に幾枚かあったのを記憶しているのである。
これは、越中においては、学塾を開き、学生を養育しても、それは空華師の弟子であり、自分の弟子とは考えていなかったようである。
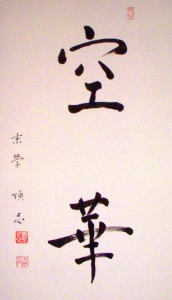 【絶対他力の思想】
【絶対他力の思想】
この学轍の思想的特色ともいうべきものは、絶対他力の主張であると思われるのである。それについては、具体的に他の学轍の学説と比較して示さなければならないが、そのことについては後に述べることにする。
その主張の根底となる絶対他力について少し説明しておこう。もし、他力という言葉を自力に対する意味で用いるものならば、絶対他力という言葉は無理である。自力という待対の意味をもつものであるなら、待対をはなれた絶対という言葉は用いてはならないのである。しかも、私は絶対他力という言葉を用いているのだが、その意味は西田幾多郎先生がもちいられる「絶対無」の意味であって、この場合の「無」とは「有に対する無」ではなく「有の無限否定」である。したがって、今いう絶対他力とは「自力の無限否定」を意味するものである。
だから、絶対他力という思想は衆生が浄土に往生するには、全部が全部、阿弥陀如来の名号・願力によるものであって、凡夫の自力的なものは無限に否定する思想であり、反面からいえば、私からは成仏する可能性を無限に否定する「絶対悪」の思想ともなるのである。
この立場にたつかぎり、浄土往生の因である信心は他力回向のものであることはもちろん、大行も名号であり、成仏の可能性としての本有仏性も否定し、宿善他力説など、往生成仏に関するあらゆる善は如来回向のものであるといわざるを得なくなり、それだけではなく、信後の生活においても、私たちの行う善的な行為は、悉く如来回向の名号の発露であるという要門助正説とならざるを得ないのである。こうした基礎的な思想的立場の理解なしには、空華学轍の主張を理解することは出来ないのである。
しかも、この絶対他力の思想こそ、浄土真宗だけでなく、あらゆる救済教の究竟的なものであり、救済教の当然いたるべき結論的な思想であると思われるのである。
 【救済の論理】
【救済の論理】
では救済教において、究竟的には、救う如来は救済力において絶対性をもち、救われる衆生は絶対悪的な性格をもつに至る必然性はどこにあるのか、その論理の基礎的なもの、またその展開の経路などについて考えてみたい。
私はその基礎的なものは、救われる者の慶びの心情であり、その心情の必然な論理性によるものであり、それを「救済の論理」といいたいのである。もちろん「救済の論理」といえば、救者である如来からの論理、救いの論理が主体となるべきものであろうが、自分はいま、被救者の立場、救われる者の心情から生ずる必然的な面を取りあげて「救済の論理」と名づけたいのである。それによって、浄土真宗の如来善の絶対性と、衆生悪の絶対性の生ずる必然の論理を究明したいのである。
救われる者の慶びの心情の構造ともいうべきものは、宗祖の説かれた「教行信証」の三哉がよくその内容を示しているようである。三哉とは「誠なる哉」「慶しき哉」「悲しき哉」の三である。「誠なる哉」は総序の文に一カ所あるだけであるが「慶しき哉」は総序の文と後序の文の二カ所にあり、「悲しき哉」も信巻の終わりと、化巻の三願転入の文の前との二カ所にある。しかも、この三哉は第二の「慶しき哉」の心情が中心になって展開されるもののようである。
すなわち、救われる者の慶びはそれは誠のものであり、真実のものでなければ慶べないのである。阿弥陀如来の願力、名号は真実であり、誠なるものであるから慶べるのである。だから、総序の文には「誠なる哉、、摂取不捨の真言、超世希有の正法、聞思して遅慮することなかれ」と説かれたのである。このことを考えると「誠なる哉」とは「慶しき哉」の内容として考えられるのである。しかもその「慶しき哉」は、遇い難きものに遇い、聞き難いものを聞いたという心情のとき、一層つよく感ぜられるものである。それが総序の文に「慶しき哉、西蕃月支の聖典、東夏日域の師釈に、遇ひがたくしていま遇ふことを得たり、聞きがたくしてすでに聞くことを得たり」と示されてある所以である。この遇い難きものに遇い、聞き難いものを聞き得たという慶びの心情は、外部的なものであって、もしこれを自分の内面的なものでいえば「救われ難き私が、今救われるとは」ということになるのである。この「救われ難き私」とは、自分の悪人という反省である。だから、自分が救われ難い存在、罪悪深重であるという意識が強ければつよいほど、救われる慶びが強くなるのである。この悪人の救われる心情をもっとも適切に示されたものが、善導大師の信心の具体的なものとして示された「二種深信」であるといってよいのであろう。悲しき哉の心情は、二種深信の機の深信にあたるものとして味わうべきである。
「悲しき哉」という言葉は、宗祖は信巻末の真仏弟子釈の結文(大信の結文とも見るべき)のところに用いられているもので「誠に知りぬ、悲しき哉愚禿鸞、愛欲の広海に沈没し、名利の太山に迷惑して、定聚の数に入ることを喜ばず、真証の証に近づくことを快しまざることを、恥づべし傷むべし」とある。
しかも、これは大信の徳を言葉を極めて讃嘆し、本願を信ずるものを真仏弟子といい、弥勒と同じとほめ「臨終一念の夕、大般涅槃を超証す」とたたえた後に記されたものである。
ここで注意すべきことは、聖人は多くの場合「愚禿釈鸞」といわれるのに、ここれは「釈」を略されているということである。このことは、自分は釈氏ではない、仏教徒としての資格もないのだという強い反省が動いていたのではないかということである。 この「悲しき哉」という自己現実の反省は、そうした悪人が今、救われていくとは・・・という慶びに変わり、慶びを新たにして深めるものである。それはいつも「誠なる哉」という、間違いのない如来の無惓の大悲につつまれている者の反省であるからである。若し大悲の救いの内省のないものなら「恥づべし、傷むべし」という言葉は出ないのである。この「誠なる哉」と「悲しき哉」とが相たすけて、「慶しき哉」を深めるものであるというべきである。
私はこの「誠なる哉」と「悲しき哉」の二を二種深信と合わせて味わっているのである。それは、「誠なる哉」のない「悲しき哉」は意味をもたないもので、救われる者の一面としてのみ意味をもつものであると考えるからである。しかも、この二は、二種深信のように矛盾性を吹くんだ一の信心の内容であるから、信心の味道の深まりとして、慶びの内容を動して行き、深めるものだといってよいでしょう。
【二種深信と三哉】
二種深信とは一信心(深心)の二性格であって、それは「どうしても救われない者」が「疑いなく慮りなく、如来によって必ず救われる」という機法二種の深信であるから、そこには「救われない者が救われる」という矛盾性をもっておる。しかも、この二種深信は決して一時的なものではなく、臨終までつづくものだといわれている。臨終まで続くということは、いつまでもくりかえす循環性であるということを示すものである。だから、二種深信とは、矛盾性・緊張性・循環性の三性質を有するものであるというのである。
矛盾性があるから、緊張し循環するのである。「落ちる者が、間違いなしに救われるとは」、だのに現実には「また落ちることばかりやっている。でも間違いなしに救われる」と、くりかえされるのである。それは「誠なる哉」と「悲しき哉」の無限の循環であるといってよいのである。
この「落ちる者が救われる。救われるのに叛いておる。叛いていても救われる」という繰りかえしが慶びを、いよいよ深めるものである。無限というものは、いつも繰りかえしによって生ずるものであり、その繰りかえしは、いつも内面的には相反する矛盾性を含むものである。
信仰の味道がたえず深まり、思想が常に深まって行くのには、その内面に含む矛盾性によるものであるといってよいでしょう。しかし、その場合に信心の内容としてその反対性である「疑」があるといってはならないのである。それは信心自身のもつ、二種深信の矛盾性であるというべきであり、それは慶びの内容を深めるものであって、往生の因法である信心が深まったり、動くと考えてはならないのである。
この二種深信の矛盾性による円環性が、救済教においては、如来の救済力の絶対性という思想になり、一面では被救者である衆生の絶対悪の思想となり、救いは如来の一方的な力によるものであり、救いに関しては衆生の参加を無限に否定する、絶対他力の思想となるのが救済教の必然的な思想というべきである。
【本有仏性の否定】
空華学轍のもっとも特色のある思想の一つには本有仏性否定の思想であろう。しかも、この思想が真宗教学の中心である行信論・助正論の基礎にもなるものであるから、もっとも注意すべきものである。
一切衆生悉有仏性という思想は「涅槃経」以来の実大乗といわれる仏教の定説となっているものであって、初期宗学においては、ほとんど問題にもならなかったのである。浄土真宗において、これが問題になったのは、宗学が研究されて、浄土に往生するのが如来の願力・名号によるものであるとの他力思想が深く考えられるようになってからである。具体的には、月筌(1671~1729)の時代であるといわれている。しかしこれが大きく問題になったのは、僧鎔・柔遠両師からだといってよいだろう。しかも、信心仏性説を明瞭に主張し、本有仏性を否定したのは柔遠からであるといってよいのである。
本有仏性の問題は、一切衆生に成仏する可能性が本来あるかどうかについての問題であって、一切衆生が成仏するという大乗仏教においては、衆生には本来仏性があるといわざるを得ないのである。因果律の立場からいえばそれは自力・他力の相違があるにしても成仏するという果が生ずることは果の生じない前に、果となるべき可能性のあることをあらわすものである。だから、それは阿弥陀如来の仏力他力によるものにしても真宗の信者が、名号を信じて成仏するのであるから、名号を信ずれば成仏するという仏性は、当然私に存在しているのだということが出来るのである。
因果律のものの考え方は、果が生じたということは、果にならない前に、その果の生ずべき因の存在を認めるものである。だから、自力他力の別はあるにしても、成仏すべき因のあることをそれ自身があらわすものである。この意味で僧叡(1762~1826)が本有仏性を「聖浄起化の宗源」と、仏性は聖道教にしても浄土教にしても、その化導のおこる根本であると、因果律の問題としたことは注意すべきであって、この因果の立場にたつかぎりには一切衆生の本有仏性は肯定せねばならないのである。
しかし、二種深信の機の深信の立場、救われて行く者の喜びの立場からいえば、私にたとえそれは如来回向の名号であっても、名号の回向にあずかれば成仏する可能性が本来あったのだと思えるだろうか。絶対他力とは、自力の無限否定だといった意味もそこにあるのである。その絶対他力の思想からいえば、本有仏性は否定せなければならないのである。
この意味では、本有仏性を肯定するか否定するかは、あくまで因果の論理の立場にたつか、信者の救いの慶びの心情に立つかの相違ともいえるのである。この点では宗学は単なる論理であるという立場を忘れてはならないのではないか。この意味で現在ひろく学界で用いられている「無自性仏性説」も、この説を説いた道振(1773~1824)も「無自性空とは仏智見の立場からいうものである」といっている。如来の立場からいえば、衆生に成仏の可能性のあること、如来との連続性のあることは論をまたないものである。絶対から相対へは連続だが、相対から絶対へは断絶であるとは、哲学者の常にいうところであって、如来(絶対)から衆生(相対)へは連続であるが、衆生より如来へは断絶であるといってよいのである。だから、この説を考えるときには「仏智見」であるということはもっとも注意すべきである。
僧鎔師の本有仏性否定の論理はあまり明瞭ではなく、柔遠師も信心仏性以外には宗祖には仏性というべきものはないと力説されているが、その論理については十分につくされたとは思わないのでありこれが完成されるのは、善譲(1806~1886)鮮妙(1835~1914)の遍満仏性説であろう。この説は十分ではないが、僧鎔師の時からあって、如来の正覚は久遠であり、阿弥陀如来は法界身であり、衆生の心中にも遍満しているからその仏性も無始より存在しているのである。だから、衆生に存在しなかった時はないがそれは衆生本来のものではなく、仏性の遍満によるものだとの主張があり、これは衆生に有する仏への志向性はことごとく如来よりのものであるという、絶対他力の思想から来るものである。
【宿善他力論】
絶対他力を主張するときには、獲信の因縁である宿善も当然、如来のはたらき、仏力他力によるものといわざるを得ないのである。
この説を完成したのは行照(1795~1862)である。師の説は「宿善とは当相自力・体他力」であるといわれている。この思想は、いまだ入信せない者にとっては自力だと思っているが、獲信者の立場からいえば、宿善そのものは如来の調熟の光明に外ならないというものである。
宿善とは獲信の因縁となるものではあるが、宿とは宿世という意味であるから、厳密にいえば「前世の善」という意味である。しかし、宿善とは必ずしも前世の善根だけではなく、獲信の前刹那までの因縁とするのであるが、この場合でも「宿」という文字のついているかぎり、それは獲信以前にいうべきものではなく、獲信者が獲信の原点に立って、この信心をいただいたのには、あの因縁もあり、この因縁もあったのだと反省した立場での名目である。だから、当相自力、体他力の思想は、宿善とは他力であり、如来の調熟の光明であるということになるのである。
宿善に自力・他力の異った学説の生ずる理由は、宿善を往生遅速の要因とするか、自己の獲信させていただいた慶びの上にたつ因縁とするかという、基礎的な態度の相違からくるものだと思われるのである。したがって、宿善そのものが自力や他力かを論ずる前に、宿善とは往生の遅速の理由を説明するものか、獲信の因縁を慶ぶ心情の立場から見るものかの決定が必要であり、そのいずれの立場にたつかによって、説の相違が分かれるのである。
それは「大経」の文
若人無善本(もし人、前世に善本がなければ)
不得聞此経(この経を聞くことは出来ない)
清浄有戒者(清い戒律を守った者でなければ)
乃獲聞正法(この正法を聞くことは出来ない)
また「御一代記聞書」(307)の
陽気陰気とてあり。されば陽気をうくる花は早くひらくなり。陰気とて日陰の花は遅くさくなり。かやうに宿善も遅速あり、されば已今当の往生あり。弥陀の光明にあひてはやくひらく人もあり、遅くひらく人もあり。
とある文などによって、衆生の往生について、已・今・当の往生の遅速のあるは宿善の厚薄によるものだと考える人々があるのである。
この人々の考えによれば、衆生の往生に遅速のあるのは宿善の厚薄によるもので、宿善の厚いものは早く往生し、薄いものは遅く往生することになるのだと考えるのである。如来の光明は平等にはたらくのであるが、平等に照らされていながら、往生に遅速の出来るのは宿善によるものだとすればその宿善とは、人間各自の積む善根であり、自力的なものとならざるを得ないのである。だから、自力とはいわないが、「自の善」だという学者もあらわれるのである。
古来、宗学においては多くの先哲は、宿善を往生遅速の論理だと考えられて来たので、自力的な色彩が強いものがあったが、「教行信証」の総序に
ああ、弘誓の強縁、多生にも値ひがたく、真実の浄信、億劫にも獲がたし。たまたま行信を獲ば、遠く宿縁を慶べ
とあり、「御一代記聞書」には
宿善めでたしといふはわろし、御一流には宿善ありがたしと申すがよく候
とあることによって、宿善とは、如来の光明であり、「よろこぶべき」であり「有難し」と思うべきであり、他力であると主張するのが、空華学轍の特色だといってよいのである。
【行信論】(何によって往生するか)
空華学轍の特色をもっともよく顕すものは、行信、助正の問題であろう。しかも、このことは、何によって浄土に往生するか(行信論)宗教者の生活はどうあるべきか(助正論)の問題であって、宗学における中心問題でもあり、本願寺派に多くの学派が生じたのも、主として行信の取りあつかい、特に大行の問題が中心であったことは、いまさらいうまでもないことである。
大行論においては「大行とは能所不二、鎔融無碍の法体大行」であるというのである。この能所不二の大行という説は、法霖の主張にもあるが、これを力説したのは僧鎔をはじめ、空華の先哲であるが「能所不二、鎔融無碍の法体大行」という言葉を用いられたのは善譲である。その意味は大行とはかたちの上では、名号でもいえるし、称名でもいえる。しかも、その所称の名号を能称の称名とは無碍一体のものであるが、その大行といわれる立場は法体の大行、如来の立場、名号の立場でいわれるものであるという学説である。
すなわち、大行といわれるものは、如来の名号であり、衆生の称名でもいわれるものであり、その名号と称名とは不離不二のものであるが、大行といわれるものは、その原点に立てば、如来の立場である法体名号が主体となるものであると説くのである。これが空華轍の一貫する大行観だといってよいのである。
この主張は、常に聖人の言葉を重要視したものであって、絶対他力の思想からいえば、大行は如来の名号だと説明すれば、思想としても、聖人の思想展開からいっても、説明しやすいものであるが行巻の大行釈には
大行とはすなわち、無碍光如来のみ名を称するなり
とあり、さらに経文の引用の終わったところには、称名破満といって、称名によって衆生の一切の無明を破し、衆生の一切の志願を満す浄土往生が出来ることを明かされてある。この二文は、明らかに衆生の称名を大行と示されたことは動かないものである。この文によると衆生の称名を大行とされたことは、文から見て動かすことの出来ないものであるから、衆生の称名を大行といわなければならなかったのである。
しかし、その大行は第十七願より出たものであるといって、標挙には
諸仏称名の願、浄土真実の行、選択本願の行
といってあり本文にも
しかるに、この行は大悲の願より出たり
といって、第十七願の五願名があげられている。だから、大行とは第十七願によるものであるということは、極めて明白なことである。しかも、その願名はいくつもあるなかで、とくに「諸仏称名の願」の願名をもちいられてあることに注意すべきものがあるのである。この第十七願の意味からいえば、大行とは「諸仏の称名」であり、私たちにとって所聞の名号というべきである。
この大行とは何かを示すのに、聖人は同一のところにおいて、一面では衆生の称名であって衆生の所聞の名号だと示されてある。この意味からいえば、聖人は大行とは衆生の称名でもあり、諸仏の称名である名号でもあると表現されているのである。すると聖人は衆生の称名と諸仏の称名である名号とは不二のものであると考えていられたことは明瞭である。しかも、その能所不二の不二の立場を軽くして能行の衆生の称名に重点をおいて能行系の学説があらわれ、諸仏の称名である名号に重点をおいて所行系の学説がおこったのである。
空華学派はその両文を認め、文の意味を十分理解して、能所不二の学説をたて、しかも、大行といわれるものは、不二ではあるが法体大行であるというのである。その意味は、大行とは諸仏の称名でも、衆生の称名でも、どちらでもいえるものであるが、その主体的な立場は「諸仏の称名」であると主張するのである。
行巻の始めに示された文を忠実にみると、大行とは「諸仏の称名」であるという表現(名号)と「衆生の称名」だという表現(称名)との二つがある。そのいづれを主とするかにより能行系と所行系との学派が出来るのである。
能行系の人々は「大行とはすなわち、無碍光如来のみ名を称するなり」と宗祖が申されているのだから、大行は衆生の称名でなければならないのであると主張するのである。この場合には、何故に宗祖は第十七願の諸仏称名の願を出されたのかが、解決しなければならない問題となるのである。
また、大行とは「諸仏の称名であり、衆生にとって所聞の名号である」と主張する所行系の学者にとっては「大行とは衆生の称名である」と申された宗祖の言葉をどう理解するかが問題となるのである。それで所行系の学者のほかには「称無碍光如来名」の「称」を「かなう」という意味で「大行とは無碍光如来のみ名にかなう」ことであると解釈する方もあったのである。しかしあの文はすなおに無碍光如来のみ名を称える、称名大行を示す文を見るのが当然である。それで空華の学者たちは、あの文によって、衆生の称名も大行といわれるのであると説くのである。それで大行とは名号でもあり称名でもある。しかも、その名号と称名とは不二であるから、いずれも大行とはいえるが、その究竟的な立場からいえば、法体である名号が主になるのであるというのが「能所不二、鎔融無碍の法体大行」という空華の説である。
では、どうして衆生の称名が諸仏の称名(名号)と不二になるのかというに、その重要な表現の一に「称即名とまきあがる」というものがある。それがこの学轍の不二の最要の表現であるとも思われるのである。それは衆生の称名がそのまま諸仏の称名である名号と「位が同じく」なるという意味であり、自分の称えた称名がそのまま聴聞の名号の位にまきあがるのだと主張するのである。
ここに空華学轍のいう「称名」の意味が、善導・法然によって説かれてきた、称名念仏と、称名の意味、念仏の意味が大いに異なるものがあることに注意しなければならないのである。すなわち、行巻の「称無碍光如来名」とは、無碍光如来のみ名を称えることではあるが、それは在来、日本浄土教で用いられて来た称名ではなく、自分の口から出て下さる南無阿弥陀仏ではあるが、それは行巻で示される「本願招喚の勅命」としての南無阿弥陀仏とするのである。
だから、この六字釈の意味からいえば「称無碍光如来名」の称名は、信後の報恩の称名ではなく、自分の口から出るものではあるが阿弥陀如来が「我に帰せよ」の招喚の勅命であり、自分にとっては聞きものという立場に立つものである。この意味で「称即名とまきあがる」というのである。
この行巻の六字釈がなければ、諸仏の称名と衆生の称名とが不二一体であるという意味が、十分理解することが出来ないのではないか。名号が称えられているのだから、能称と所称とが不二だといわれても十分ではないが、私の称名が単なる仏名を称するものではなく、如来のよび声であり、本願招喚の勅命であり、称えながら聞きものである場合でハッキリと称即名といえるのである。
それは諸仏の称名は、私にとって聞きものである。もし私の口から出て下さる南無阿弥陀仏が如来のよび声であったら、私の口から出るものではあるが、私にとっては「聞きもの」である。諸仏の称名も聞きものであり、私の称名も聞きものであるという立場にたったとき、はじめて純粋に「私の称名」が「諸仏の称名」と不二一体になるのである。そこにはじめて能所不二であり、しかも、所称の法体の名号を大行という説が成立するのである。
この意味で行信論を論ずる場合行巻の六字釈は注目すべきものではないか。経文の引用が終わって称名破満が説かれ、龍樹以下五祖の引用が終わった私釈に六字釈を出しその名号によって必得往生と示されているのであるが、この帰命釈は在来の解釈とは全く異なった解釈をほどこし、衆生のものであるべき帰命を如来の勅命とされたのである。これは在来の称仏名は衆生の称名であったものを、諸仏の称名と同じく、衆生は称えながら所聞の位で味わうべきことを示されたもののようである。この立場で「称無碍光如来名」を理解しなければ「称即名とまきあがる」とか「衆生の称名がそのまま諸仏の称名と同位になる」という意味が理解されないのである。
【助正論】
空華学轍の特色のもっともよくあらわれているものの一つは「助正論」である。助正論は宗教生活の問題であるから、宗教者としては大切な問題であり、重大なものであるが、その生活の上にも、絶対他力の思想に立つか否かで、考え方の相違が生ずるのである。
助正論は広島において、大瀛門下と僧叡との争いによって有名になり、問題ともなったのであるがそれは、報恩行に助正ありや否やということで、大いに議論されたのである。僧叡は弘願の報恩行に助正があり、正業といわれるものは称名であって、読誦等の四法は助業であると主張するに対して、大瀛門下の人々は助正というは往生業についていうことであって報恩行には助正の区別はなく、平等である、助正があるというは往生の因についていうことで要門分斉であるというのである。
空華学轍はもちろん、弘願の報恩行には助正なしという説をとるものであって、報恩行はことごとく名号の顕現にほかならないのだというのである。往生の因法について、衆生の自力的なものを無限に否定する絶対他力の思想は、報恩行についても、仏祖の報恩の行となるべき善的なものは、ことごとく如来回向のものであり、回向の名号の顕現であるというのは、その思想傾向からいって当然であろう。
第一弘願助正説において、南無阿弥陀仏の名号が称名にしか顕れないというのは、あまりにも名号の意味を狭くとっていないか。もちろん、善導、法然の二師は称名に力を入れて、念仏とは称名にかぎるものであり、称名に最高の価値を認めて、浄土教においては称名はもっとも価値あるものとされたが、報恩行にまで、称名の価値だけを高く意味づける必要があるのであろうか。名号は称名だけにしか顕現しないという思想は、名号の意味を十分理解しているとはいえないのである。
名号とは「大経」によると、その仏の徳を広く讃嘆する広讃の意味である。経に名号の内容を明瞭に示されてあるものは、第十八願成就文の「聞其名号」のところだけである。その文は第十七願、第十八願成就文の
十方恒沙の諸仏如来は、みなともに無量寿仏の威神功徳の不可思議なるを讃歎したまふ。あらゆる衆生、その名号を聞きて、信心歓喜せんこと乃至一念せん
とあるところに名号の内容が示されてあるのである。この文によると、名号とは十方恒沙の諸仏如来が讃嘆したもう、無量寿仏の威神功徳の不可思議なることであり古来「広讃」といわれるものである。もちろん、称仏名には「観経」下品に説かれる「南無阿弥陀仏と称えるもの」もあるのである。だから、先哲は讃嘆には広讃と略讃とあるといわれ、少なくとも「大経」では名号とは広讃の名号となっているのである。この意味からいえば、四十八願の中にいく度も「聞名」といわれるものは、第十七願成就文の諸仏の広讃の名号を聞くことだというべきである。
また、宗祖は教巻において「大経」の真実教であることを証明するために示された三論理のなかの第三に「名号為体」の経なるが故にとある。すなわち「大経」が真実教といわれるのは、第一には釈尊出世本懐の経であるから、第二には一切衆生を無条件で救う第十八願が中心の経であるから、第三には、名号を体質とした経であるからと説かれてある。この「名号を体とする」ということは、その経のどの部分にも名号の行きわたった経であり、経の全部が名号讃嘆にほかならないという意味である。この意味からいえば、釈尊が説かれた「大経」は、阿弥陀如来の徳の広讃にほかならないのであるから、私たちが読経するということは、釈尊が名号の広讃歎をなさったのを口まねしているのだから、略讃の称名と同じ意味だといってよいのである。
このように味わってくると、読誦は名号の広讃であり、称名は名号の略讃であるから同価値のものといえるのではないか。讃歎についても同様のことがいえるのではないだろうか。
空華学轍においては、衆生には本来善根といわれるものは、まったくないものだと説くものであるから、報恩行という善的なものも、私の本有のものではなく、如来回向の名号が微々としてあらわれるものだと説くのである。だから、称える称名はもちろん、おがむ手も、うなずく頭も、ことごとく如来回向の名号の顕われであるというのである。したがって、報恩行としては、同じく名号の顕現であるから、いずれの行も同一の価値で主伴をつくべきではないと説くのである。
弘願助正では、称名だけが名号の顕現であって、読誦・観察・礼拝・讃嘆供養は、如来回向の名号のあらわれた称名に随伴して、人間の本来有したものがあらわれるので、名号の顕現は、ただ称名にかぎるものであり、読誦等は名号のあらわれではないと主張するのであるから、名号の広讃を許さないことになるのである。
南無阿弥陀仏の名号には、そんなせまい限界をつけなければならないものだろうか。蓮如上人が「御一代記聞書」に
万事につきて、よきことを思ひつくるは御恩なり、悪しきことだに思ひ捨てたるは御恩なり。捨つるも取るもいづれもいづれも御恩なり
とある。この場合の御恩というは「お恵み」の意味である。だから、この文は、人間の一切の止悪も作善もことごとく如来のお恵みだと教えられるものである。また同じく「聞書」には
丹後法眼(蓮応or蓮慈?)衣装ととのへられ、前々住上人の御前に伺候候ひしとき、仰せられ候ふ。衣のえりを御たたきありて、南無阿弥陀仏よと仰せられ候ふ。また前住上人(実如)は御たたみをたたかれ、南無阿弥陀仏にもたれたるよし仰せられ候ひき。南無阿弥陀仏に身をばまるめたると仰せられ候ふと符合申し候
とある。蓮如上人は、しばしば自分の所有する者に対して「如来の御用物」とか「如来聖人よりたまわりたるもの」と申されているが、それがさらに深化すると南無阿弥陀仏の具体的なあらわれであると考えられていたようである。それがお衣を南無阿弥陀仏といい畳を南無阿弥陀仏といい、自分の周囲をとりまくものはすべて南無阿弥陀仏であると考えられていたのである。
この蓮如上人の教示からいえば名号は略讃の称名となってあらわれるはもちろん、広讃の讃歎として現れるだけではなく、私を生かしめるための、あらゆる物として顕現するものであるといえるのである。だから、拝む手も、称える口も南無阿弥陀仏といった先哲の言葉もうなずけるのである。
このように名号の顕現を拡大して考えるところに、名号の真実の徳が発揮されるのであり、如来の名号成就の意味も明らかになるのである。もし、名号が称名にしか顕現せないものであり、称名だけが報恩の正行だとすれば、現実の寺院の法要などにおいて、僧侶は価値の低い助業を主としているのではないかという非難は当然うけなければならないのではないか。名号は単に略讃としてあらわれるだけではなく、広讃としてあらわれ、釈尊の広讃が三部経であり、しかも、私たちが読誦する聖典はことごとく名号の広讃とすれば、読経することはそのまま名号の顕現だということになるのである。
かく考えると、報恩行には助正なしという思想が十分是認さるべきものである。
以上きわめて大略ではあるが、私がいままで教えられてきた、空華学轍の学説の特色について述べてきたのであるが、宗学とは浄土真宗においては、救われるものの慶びの論理を示す学であり、救済の論理の学であり、絶対他力の思想によって進められる学問でなければならないと思われるのである。
・・・完・・・
> 空華の里
> 明教院釈僧鎔を訪ねて
> 実のないイチョウの木の話
> 空華学轍の思想/桐谷順忍
> 僧約
> 専精会
>> 黒部市HPより