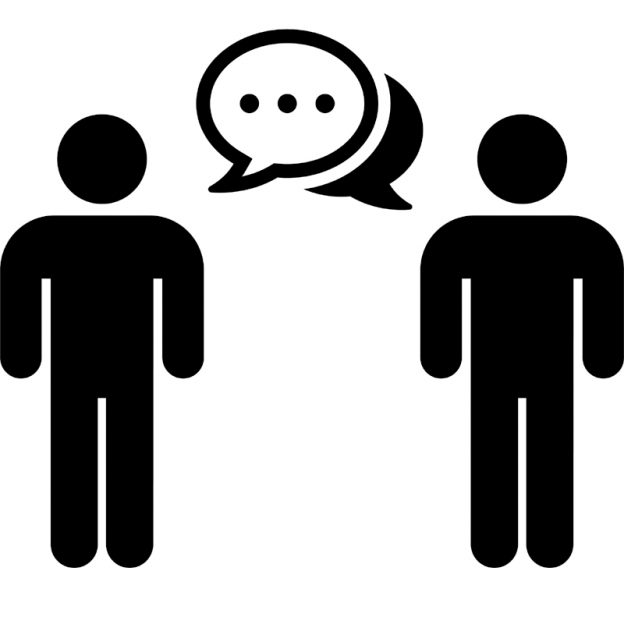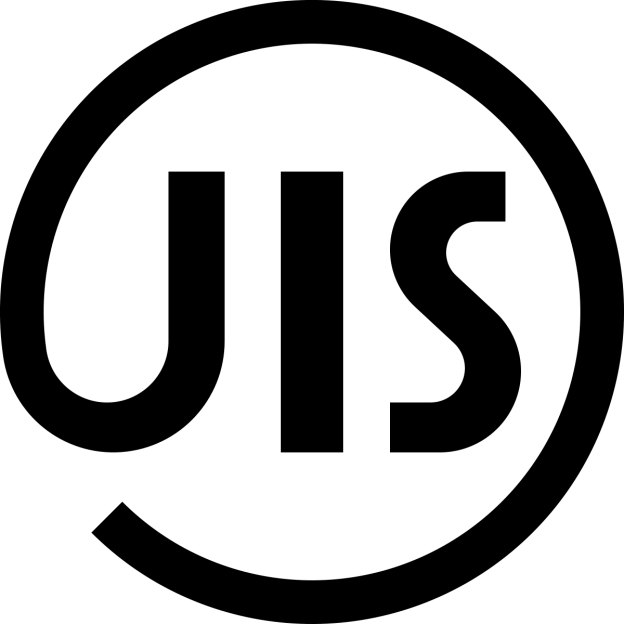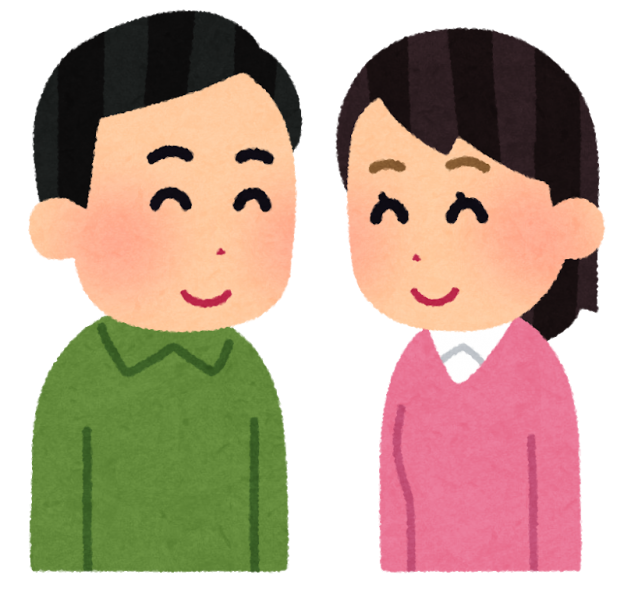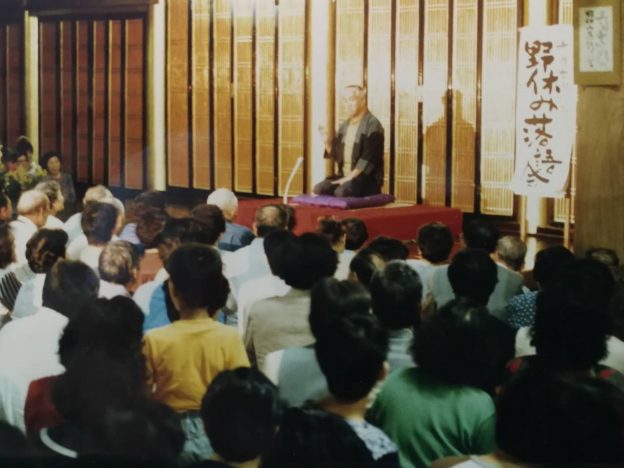Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: RSS
昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。
「モシモシ、おたく、水子、やってくださいます?」
―?!(ナンノコッチャ)
「近頃、体の調子がおかしくて困ってましたら、知り合いが、みてもらえっていうんです。それでみてもらったら、私には何か迷った霊がついているとかで、それをなんとかしないかぎり、不幸がつづくといわれましたの。それで、もし、おたくのお寺でお経読んで下さるんでしたら、わたし、これからうかがおうかと・・・」
―あなた、いま、どちらから?
「東京なんですけど」
―アホかいな。宇奈月の温泉につかりにくるのならまだしも、わけのわからんことで私のお経を聞きにきても、なんにもなりませんよ。それより、体の調子が悪いのなら、お医者さんへゆきなさい。病気になったら医者へ行け、とおしゃか様もいっておられます。
「でも、みてくれた人が・・・」
―ほれ、またはじまった。みてくれた人がっていったって、その人一体どんな人なの?あなたのことをあなた以上に知っている人なの?なに?なんでもよく当たる人?バカおっしゃい。クイズの王さまでもあるまいし。いまの日本中の女性のほとんどが、その水子の霊とかいうと、思い当たることになっているんでしょ。あなたそんなもの信用してどうしようというの?
「ですから、このなにかモヤモヤしたものをスッキリさせたくて・・・」
―バカタレ!(面と向かってならいいにくいが、電話だと、つい、こういいたくなっちゃう)あんたのモヤモヤをスッキリさすために、水子の霊をしずめるなんて、因果の道理に合わんじゃないですか。私は浄土真宗の坊主だから、ハッキリいいますがね、あなたの気持ちもわかるような気はするが、いま世間でいう水子供養なんてものは、ほとんどがインチキだよ。何万円かでコケシみたいなの売りつけて、あんなもので浮かばれたとかなんとかいうのかね。冗談じゃないよ。自分の責任を上手にすりかえて、水子に押しつけ、おまけに、その供養を坊主にたのむとはいったいどういうこと?あなた何もしてないじゃないの。ただ自分のモヤモヤをスッキリさせたいため、迷っている子供を・・・なんていってる。子供は迷っていません。ええ、ゼッタイあなたが思っているような迷い方してませんよ。いいですか。迷っているのは、奥さん、あなた自身なんですよ。他人のせいにしちゃいけないよ」
「・・・やっぱり・・・そうなんですね」
―?
「じつは、私もそうじゃないかと思ってたんですが、やっぱりそうだったんですね」
―なんだ、わかってるんじゃないの。
「ええ、でも、そういうふうにいってくれる人はいなかったんです。だれに聞いても、たたりだとかついてるとか、ひどいことにはお医者さんでも、おはらいしてもらえなんていう人いるんです。それで、もう、わたし、わからなくなって・・・」
―あなたも悪いが、まわりも悪いなあ。
「ハイ、子供の命の分までなんとか精一杯がんばります」
そう、迷っているのは、霊とかなんとかいういいかげんなもんじゃなく、じつは、わたしたち自身だってこと、気づかなくっちゃあね。
「お茶の間説法」(37話分)
>> https://www.zengyou.net/?p=5702
>>「お茶の間説法」 プレイリスト
>>「続・お茶の間説法」 プレイリスト