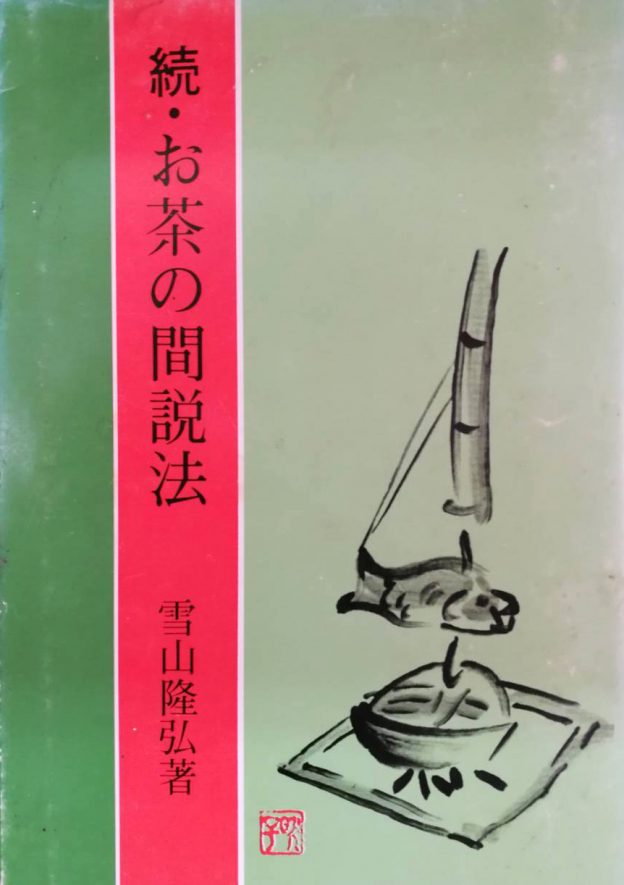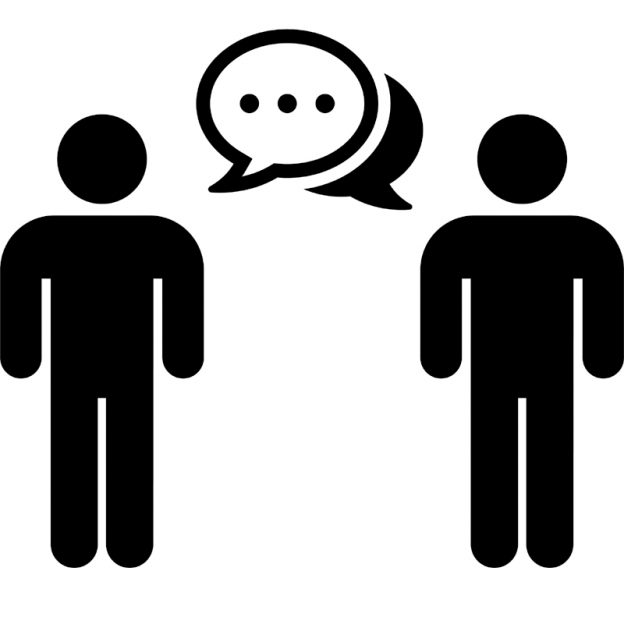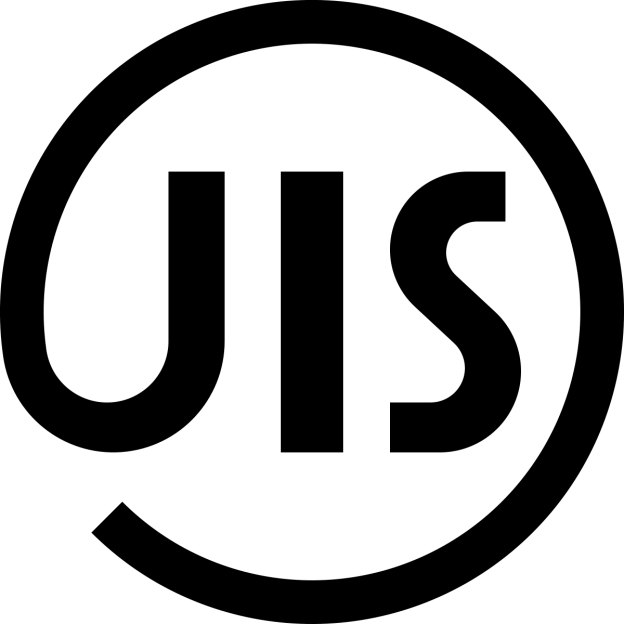「コロナに負けるな」という言葉に違和感がある。言わんとするところはわかっているつもりで、「厳しい状況だけどみんなで力を合わせてがんばろう!」とか、学校なら、「手洗い検温を忘れずに気を付けよう!」とか、とにかく「気落ちせずにみんなでがんばっていこう!」ということを、まるっとまとめて「コロナに負けるな!」と言っているんだろうけど、そもそも、勝ち負けに単純化して現している点が腑に落ちない。
負けるな、って何だろう?
コロナにかかったら負けなのか?
コロナ感染者の人がその垂れ幕を見たらどう思うんだろう・・・。
前回の一口法話にも、健康第一という言葉が不健康な人を傷付けている場合がある、という話が出て来たけど、まさにそれと同じことだと思う。
ある女流作家で、体の弱い方が、こんなことをおっしゃていたのを聞いたことがあります。
「わたしは、心臓が弱く、いつ発作が起きるかわからないというとても不健康な人間です。そのわたしが、本当に腹立たしく思うのは、世間の人の会話の中の、健康に関するものです。なんといっても健康第一とか、体が悪くないのが一番の宝とか、元気であることが財産ですとか、そんな会話を聞くたびに、どうして世の中の人は、健康のことばかりいうんだろう、と思うんです。だって、不健康なものにも、人生はあるんですよ。不健康なものの人生にもよろこびはあるんですよ」
http://www.zengyou.net/?p=6021
健康でありたいという願いも、コロナにかかりたくない願いも、それに萎縮したり気落ちしたりしたくない願いも、よくわかるけど、それをスローガンとして「負けるな!」というのは、間違った言葉使いじゃないかしら。多数派率いて奮起するがごとくにスローガンにしてしまうのはいかがなものだろう。少し歩み寄った言い方をすれば、日本中が動揺した4月前後にそういう言葉が出てきたのは仕方ないにしても、ウィズコロナという言葉もある中で、そろそろ表現を変えてもいいんじゃないかと思う。水を差すのは心苦しいんだけど、ひいては、いのちの尊厳にも関わってくる問題だと思うので、物申さずにはおれなくて・・・。
拡大解釈になるけど、詰まるところ、根底には老病死の取扱いに問題があるような気がしている。老いることも、病になることも、死んでいくことにも意味を見出していく仏教とは真逆の考え方で、現代がそこにがっちりフタをして遠ざけてしまったにしても、さらに拍車をかけているような印象でゾッとする。老病死に価値がないなら、使い捨ての道具と同じで、そこには命の尊さなんて微塵もない。
少数派の声だということは自覚してる。でも、そういう多数派の声が少数派を苦しめている現実も知っていただきたく、あえて書き残しておきます。これには、教育現場である学校にも垂れ幕があったのを目にして、子供たちが大人が作った言葉を借りてチョイスしているのは想像に難しくなく、それがあまりにもショックで。そんなスローガンを見ながら子供に育ってほしくない・・・。勝ち負けの世界ではあるけど、それがすべてだとしたらみんな負けに向かってまっしぐらの人生やろ。感受性豊かな子は気付くよ。
このスローガンを掲げてがんばっている人たちには水を差してしまうことになったけど、意図せずとも傷つけてしまう人たちがいることをどうぞご理解下さい。私も言葉を単純化して、知らずに誰かを傷つけていることを持戒しつつ。