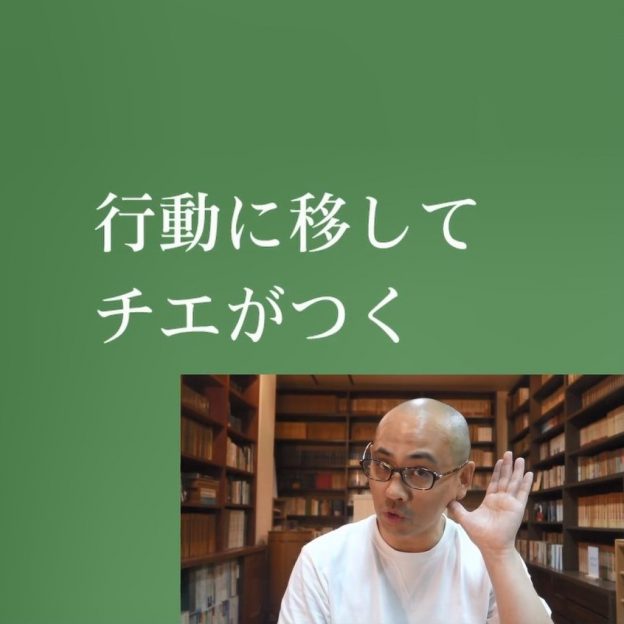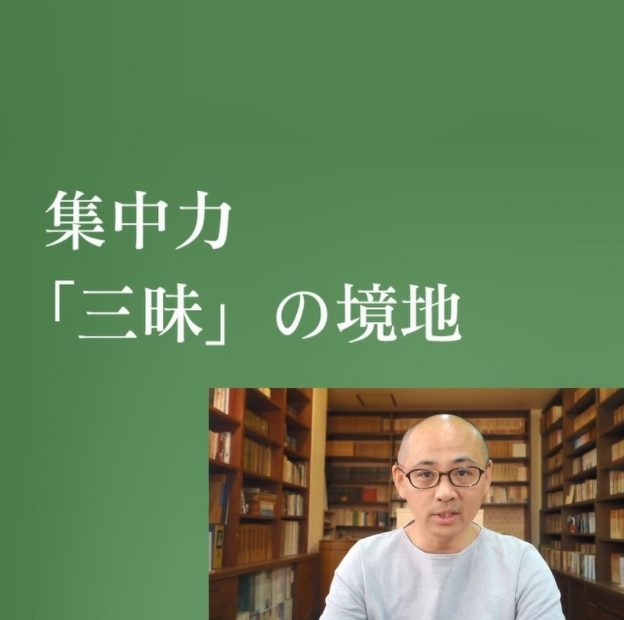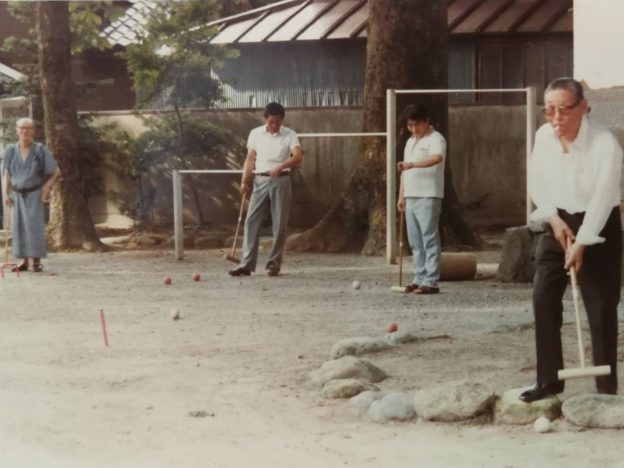Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: RSS
昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。
名人、達人になる方法のおしまいは「チエの目を開け」ということであります。事に臨んで智慧がなく、正しい判断ができないようでは、いくら力があってもうまくはゆかない。
で、この智慧の目を開くにはどうすれば良いかといえば、聞(もん)、思(し)、修(しゅ)の三段階があるといわれていて、耳で聞き、思索し、それを修得してゆくわけです。これはなかなか味のあるところで、聞いただけでは智慧とはいわず、考えただけでも智慧とはならず、これを身につけて行動に移してこそ、はじめて智慧ある人と呼ばれるんです。
いつだったか、将棋の大山名人の名人談義を聞いたことがありますが、将棋で1番むずかしいのは、自分の負けを自分に納得させるときだそうで、なるほどなあと思った。ね、ホラ、いまわたしは、名人の話を聞いて、なるほどと思ったといったでしょ。聞いて思ったんですよね。ところが、3番目の「修」つまり体で覚えるというところが抜けているから、大山さんの智慧が身についたわけではない。それどころか、相変らず、負けを負けと知らず、負けるはずがない、そんなはずはないと、浅ましくもハラを立てたり、グチをこぼしたりの毎日です。
まあ、それはさておき、その大山さんの名人談義-ある時、名人戦の対局で、ある旅館へ出向いた。そして、いよいよ勝負がはじまり、それこそ、全神経を集中させ、智慧をしぼっての対局となった。
序盤戦。局面の展開を見ないまま休憩となった。名人たちが席を立つと、そこへ1人の男がはいってきた。ジッと部屋の中のある1点を凝視して、すぐに引き下がった。そして、この男がつぶやいた。
「部屋にはいって右側の人が勝ちだな」
勝負は始まったばかりで勝ち負けは本人にもわからないときなのに、こういってのけた。で、勝負はズバリ、右側にすわっていた大山名人が勝った。
対局のあと、この話を知って、大山さんはびっくり。部屋をちょいと見ただけで、どうしてわかったのだろうと旅館の人に聞いてみた。そしたら、なんと、この人はフトン屋さんで、将棋は素人。たまたま、対局用の座ぶとんを新調して、それに名人がすわられるというのを知って、どうしても現場を見てみたいといいだし、休憩中にこっそり・・・ということになったのだという。
でも、なぜ名人の勝ちとわかったのか、といいますと、このフトン屋さん、盤面で判断したわけでなく、自分のつくった座ぶとんでわかったのだといいます。左側の座ぶとんは前の方に重みのかかったあとがあり、これはあせりの証拠と見てとり、一方の右側をみれば、後に重みがかかったあとがある。これは落ち着いている証拠だから、右側の勝ち、といったのだそうです。将棋の名人はふとんの名人に1本とられたと大いに感嘆した、ということであります。
智慧の目-それは、多くの「聞」と、深い「思」と、きびしい「修行」の中から生まれる迅速適切な判断、的確妥当な処置や行動をなすことができる能力であります。われら凡人に1番欠けている目ではありますが、なんとか少しでも身につけたいと願わずにはおれません。
あぁ、また、やっちゃった。修行抜きの願いなんて、何の役にも立たないのにねー。やっぱり、程遠いか、名人、達人は。
「お茶の間説法」(37話分)
>> https://www.zengyou.net/?p=5702
>>「お茶の間説法」 プレイリスト
>>「続・お茶の間説法」 プレイリスト