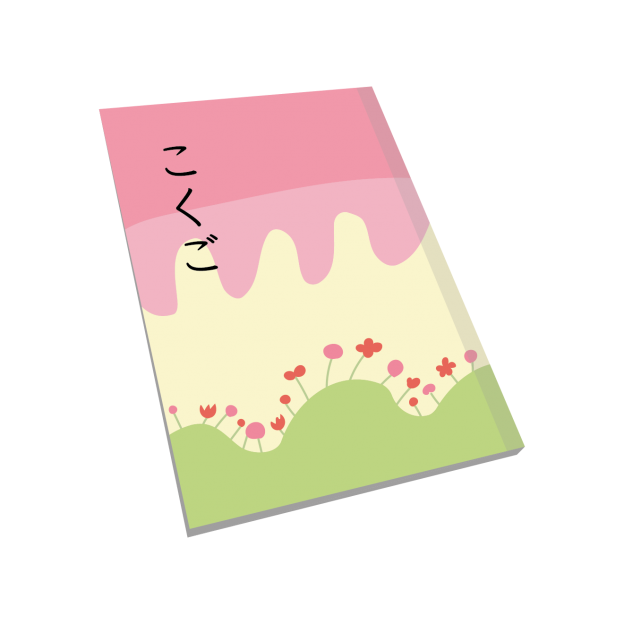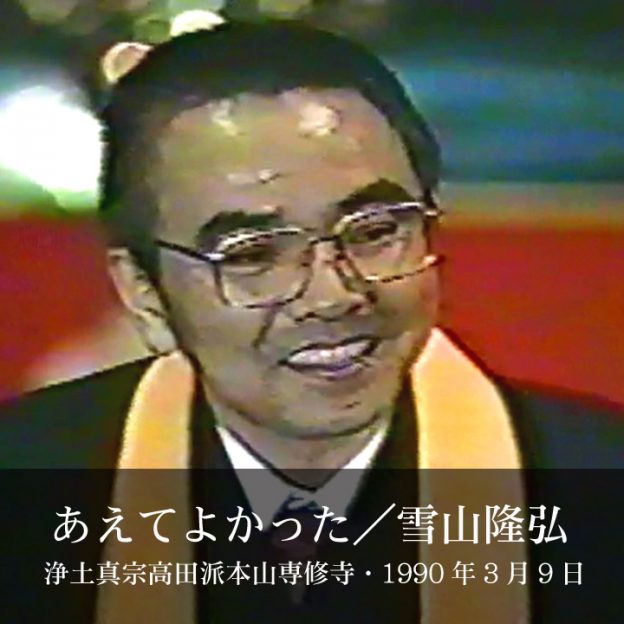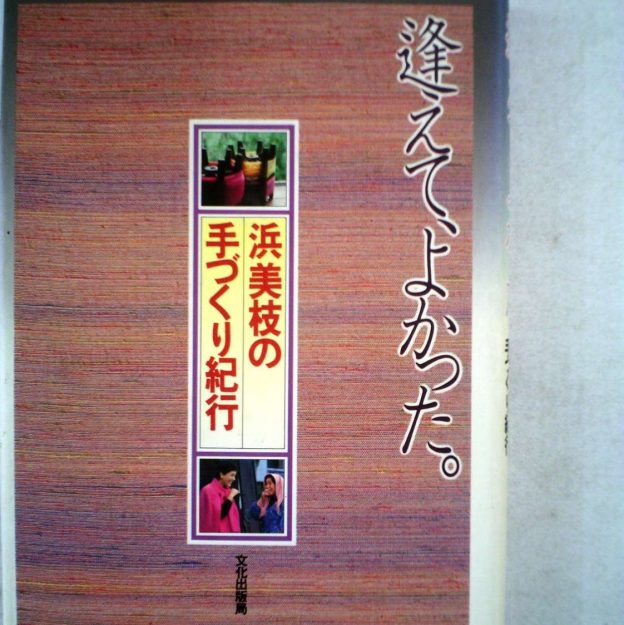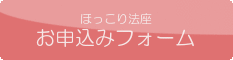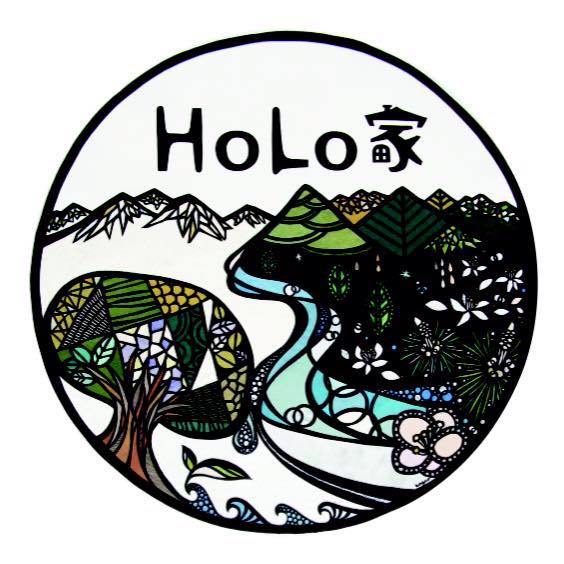Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: RSS
「うちのお母さんのころの教科書はね、若ハン」
と、76のおばあちゃんがいうからすごい。このひと、ずいぶんかしこかったそうな。なるほど、あんたのお母さんの教科書まで覚えてるの?
「ハイ、というても、全部はいえませんちゃ。けどね、なにやら、キミ タミ オヤ コ というのだけ覚えとります」
キミって、あんんたのキミじゃない方のキミのようですな。タミも、タミちゃんのタミじゃなくて、民の方みたいですな。オヤ コは親子か・・・、ナルホド。で、おばあちゃん、あんたの小学校1年の教科書は?
「ハイッ!」
オホッ、おばあちゃん、小学生に返ったぜ。手まであげて、元気なもんだ。それではどうぞ!
「ハナ ハト マメ マス ミノ カサ カラカサ!本に描いてある絵まで覚えてますちゃ。あっ、違うた違うた。これは妹のやわ。モトイ!そう、わたしのは、ハタ タコ コマ ハト マメ・・・そう、これでした、ハタちゅうたら、日の丸がパチッと描いてありました」
すごい記憶力。おばあちゃん、よっぽど秀才だったんだね。そんならもう一つ。今度は2年生の教科書はどうですか?覚えてますか?
「ありゃ、忘れました」
そう、そんなものなんですね。はじめて開いた教科書の印象というのはものすごく強烈で、あとのはもう惰性みたいなもんだから覚えてないんでしょうなあ。
「若ハン。私らのは サイタ サイタ サクラ ガ サイタやったです」
と、さっきよりひとまわり若いおばあちゃん。こっちの方には、うなずく人が多かった。と、そばの奥さんは、
「私ら、もちっと若いもん、さっき若ハンいうとられた、ヘイタイサン、でした。でもコンニチワじゃなくて、ススメ ススメ チテ チテ タ トタ テテ タテタでしたよ」
今日の茶の間は年齢層が幅広いなあ。まあそれで、みなさん、適当に昔を思い出して、若い頃の気分にひたっていただければ、もう、私の説教はいらんわけですが、ちょっといわせてもらうと、やっぱり、小学校1年の教科書はすごい、こわ、ということです。
キミ タミ やらヘイタイサン・・・ちゃんと時代を背負っていますわな。そして、その次はなぜか、ハナやら、みんな いいこ やらになる。で、習うた子は、それがどうしてそうなったのやらわからずに、とにかく覚えて身につける。仏教ではこういうの「薫習(くんじゅう)」といいます。印象づけられたものが心にしみつくことでありまして、近頃ではこれを「すり込み」なんていうようです。ちょうど、ものの香りが身にしみつくように、はじめに習うたものは、心にしみついて消えないものらしい。
で、これが長いて、その人の香り、臭みになってゆくわけでありまして、もちろん、他のご縁もいっぱいあるけど、だいたい、キミ タミ と、ハタ タコ と、サクラ ガ サイタと、チテ チチ タ と、みんないいこ が鼻面突きあわせていたら、お互い他人のにおいが、肌に合わず、しまいには、ハラ立ってくる。困ったもんやねーといったら、みんあそろって「そやそや!」
昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。
「お茶の間説法」(37話分)
>> https://www.zengyou.net/?p=5702
>>「お茶の間説法」 プレイリスト
>>「続・お茶の間説法」 プレイリスト