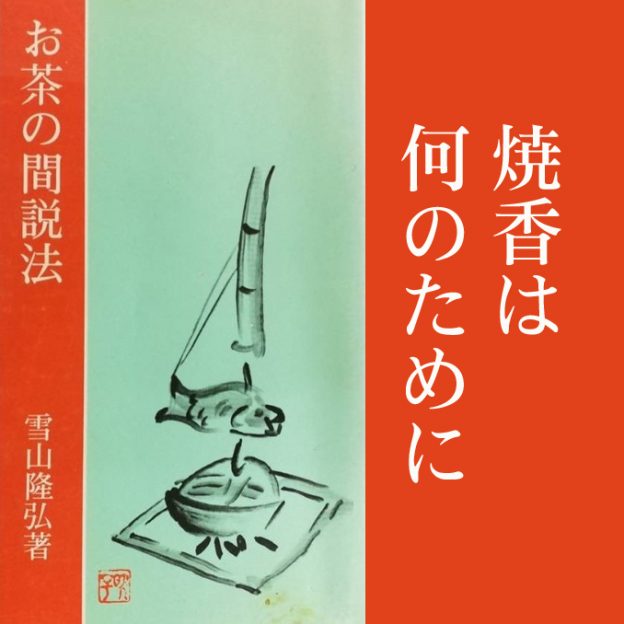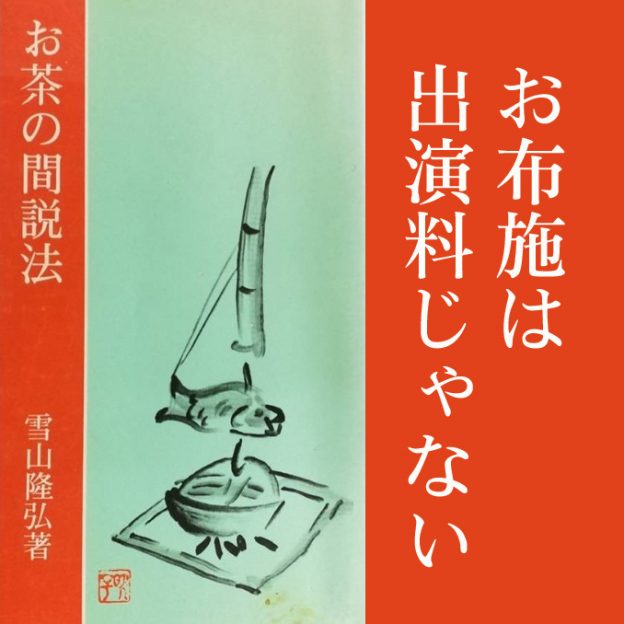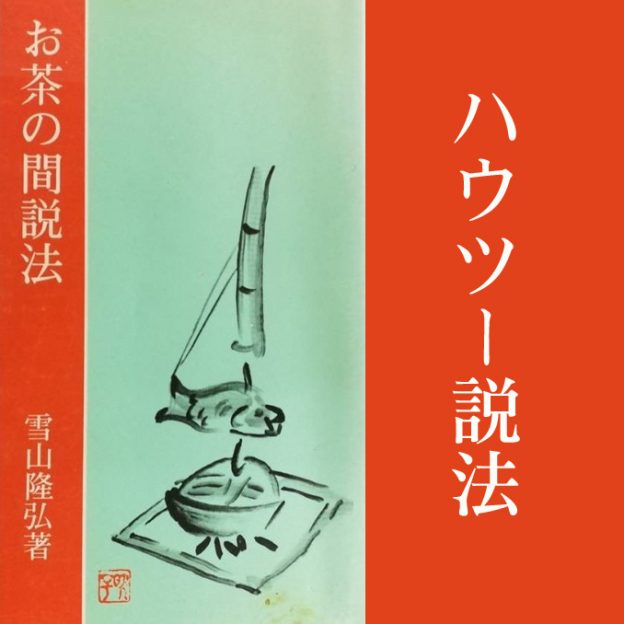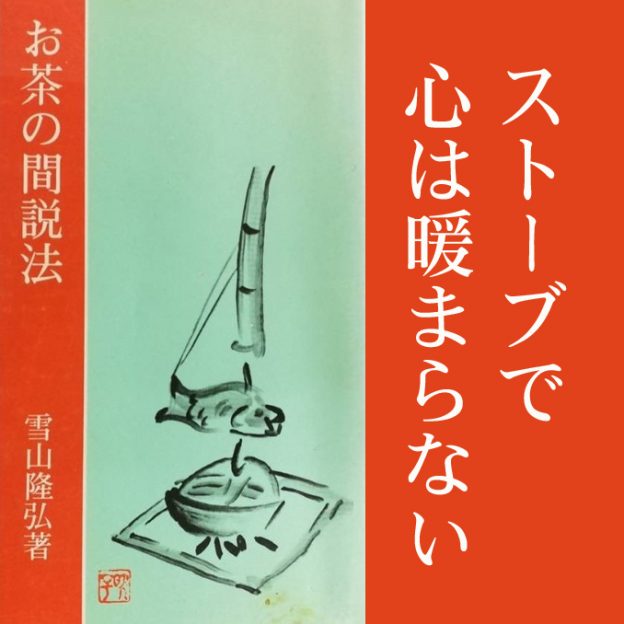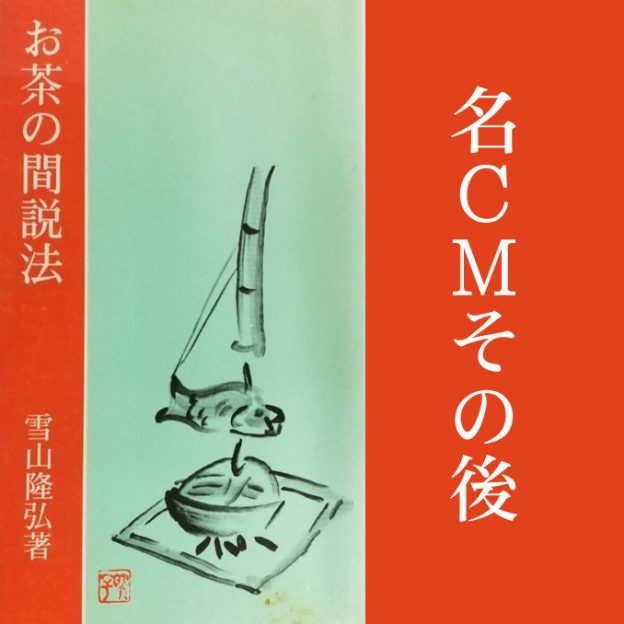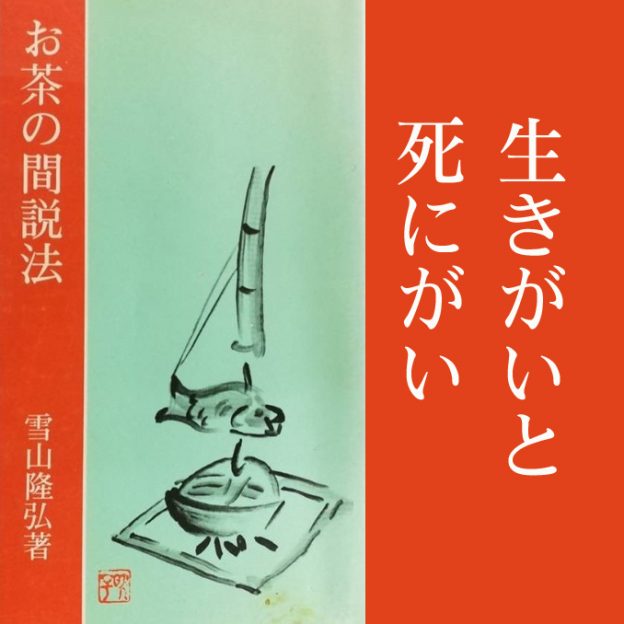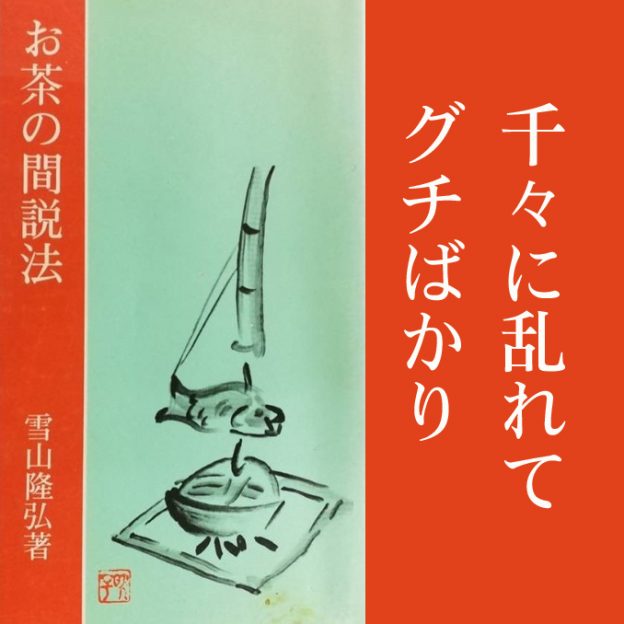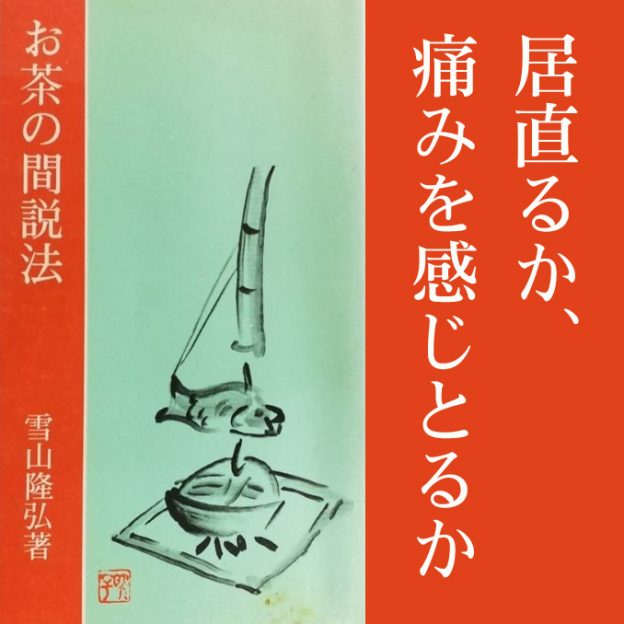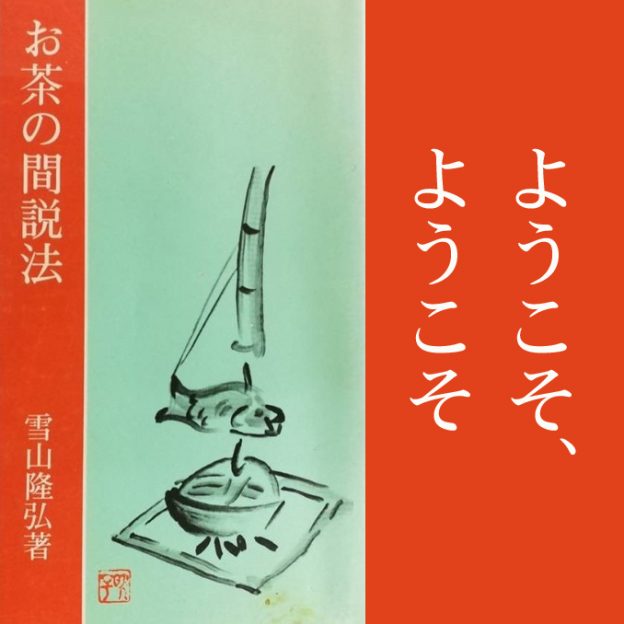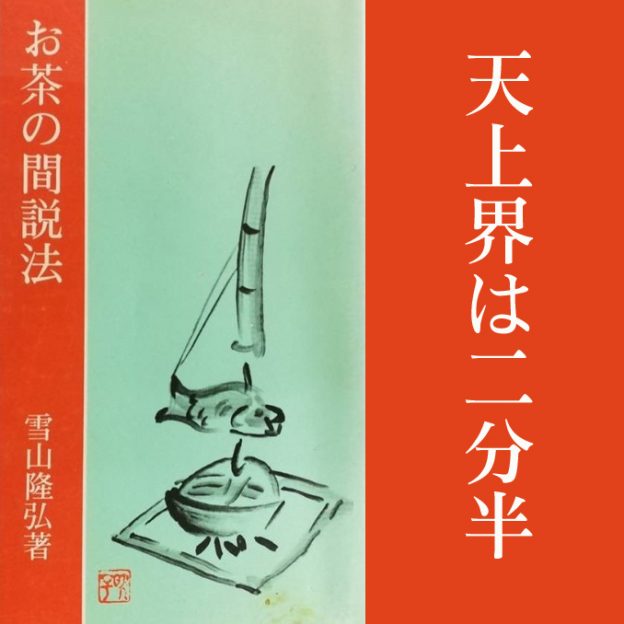Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: RSS
昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。末尾には、著者本人による録音音声があります。
きょうは香りというものについてお話をいたしましょう。といっても、わたしは香りに関する専門家ではありませんから、思いのままに話させていただくわけですが、だいたい、この香りとか、においというものに対して、日本人はずいぶんと鈍感だと思うのです。中でもとくに男性はひどくて、クルマや電車や、せまい部屋の中でもおかまいなしに、ヤニくさいタバコのにおいをふりまき、酒のにおいをムンムン発散させて、ちっとも他人に迷惑をかけているとも思わない。ちかごろようやく、嫌煙権などというめずらしいことばを持ち出して、くさいにおいはおことわり、プラットホームでは吸わないで、などという方たちが出てきたようでありますが、それでもやっぱり鈍感な人は鈍感です。
そして、女性といえば、男性に比べてすこしは進んでいるようにも見えますが、それはご自分の化粧品に関してだけのこと。いかに甘い香りをふりまくか、ということには神経つかっていらっしゃるようだけど、では、わが家の香りというものについてはどうかといえば、そこまで手が届いてはいないようです。
嗅覚というものは、本来、動物が食物の存在を知り、その適否を判断し、異性を求め、あるいは外的から避けるなどのためにある感覚だ、ということですが、近頃のわれわれは、食物はスーパーに、異性は目の前に、外敵はお巡りさんがめんどうみてくれる…ということで、嗅覚はまるで必要なくなったようです。ですから、石油ストーブのけむる部屋で、鼻をつくようなヘアスプレーや化粧品をふりかけた家族が、テーブルをかこんで微なる香りのワインを飲み、油いためと焼魚とたくあんを食して、ちっとも違和感を感じない。少々鈍感すぎるんじゃないかと思うんです。天人からみれば、そうした人間の悪臭は、なんと四十万里四方に漂っているのだといいます。ちょっと気味が悪いですね。
ところで、こんな話をするのは他でもありません。ハウツー説法、今回は「焼香とはなんぞや」ということを考えてみたかったからなのです。焼香といえば仏事のお作法で、抹香をつまんで香炉の中へチョイと入れる。あれはいったい何回つまむのか、また、つまんだ抹香は押しいただくのかどうか…これもよく聴かれることでありますが、その答えは後まわしにして、また、なぜ焼香というものをするのか、考えてみましょう。
先ほども申しましたように、人間というのは、においに鈍感になってしまいましたが、天人からみれば不浄なるもの、悪臭プンプンたるものということになるのです。そこで仏事を営む折には、せめて、この身の不浄なる悪臭を消すために、つまり、わが身を清めるために香をたくのだという説があるのです。そしてまた香をたくと、その香りによって、敬けんかつ、おごそかな気分になって、心を落ちつかせ、邪念をうちはらうという効果もある。
ですから、焼香というのは抹香そのものをお供えするのではなく、香をたくということに意義があるわけで、抹香をつまんで押しいただく必要はありません。しかし、いろんな宗派によってこだわりがあって、1回だとか、2回だ、3回だといいますが、回数にこだわることもないでしょう。ただ気をつけていただきたいのは、あくまでも焼香は、香りに値打ちがあるのですから、タヌキやキツネをいぶりだそうような、そんな抹香は使わないようにしましょうよ。香をたく場は、わが家で最も清らかで、いちばんよいにおいのするところにしたい。そうでないと、またまたこんな話、抹香くさいといやがられます。このことばは、おそらく、安物の抹香を使いすぐた家か寺から生まれたのでしょうからね。
雪山隆弘
昭和15年生まれ。大阪・高槻市の利井常見寺の次男として生まれ、幼い時から演劇に熱中。昭和38年早稲田大学文学部演劇専修を卒業後、転じてサンケイ新聞の記者、夕刊フジの創刊メンバーに加わりジャーナリスト生活10年。されに転じて、昭和48年に僧侶(浄土真宗本願寺派)の資格を取得し翌年行信教校に学び、続いて伝道院。同年より本願寺布教使として教化活動に専念する。善巧寺では、児童劇団「雪ん子劇団」をはじめ永六輔氏を招いての「野休み落語会」など文化活動を積極的に行う。平成2年門徒会館・鐘楼建設、同年往生。
<-目次-「お茶の間説法」>
・お目覚め説法
・いい天気ってどんな空?
・カガミよかがみよ鏡サン
・心のファウンデーション
・決めた!はヤメタのはじまり
・だいどこ説法
・スプーンはおいしさを知らない
・ひとりいきいき
・いただきます、してますか?
・おかげさま?おカネさま?
・るす番説法
・あなたのダンナは本当の旦那か?
・ベルの音いろいろ
・長屋とマンション
・ひとりよりもふたり
・いどばた説法
・浜美枝さん
・六道はいずこに
・この世はあなたのままになるか
・天上界は二分半
・ようこそ、ようこそ
・居直るか、痛みを感じるか
・千々に乱れてグチばかり
・生きがいと死にがい
・名CMその後
・ストーブで心は暖まらない
・ハウツー説法
・お布施は出演料じゃない
・焼香は何のために
・仏だんの意義
・ありがとう、さようなら
・お茶の間説法
・焼きイモの味
・女のよりどころ
・男は富貴
・煩悩はいくつある
・チャンネル説法