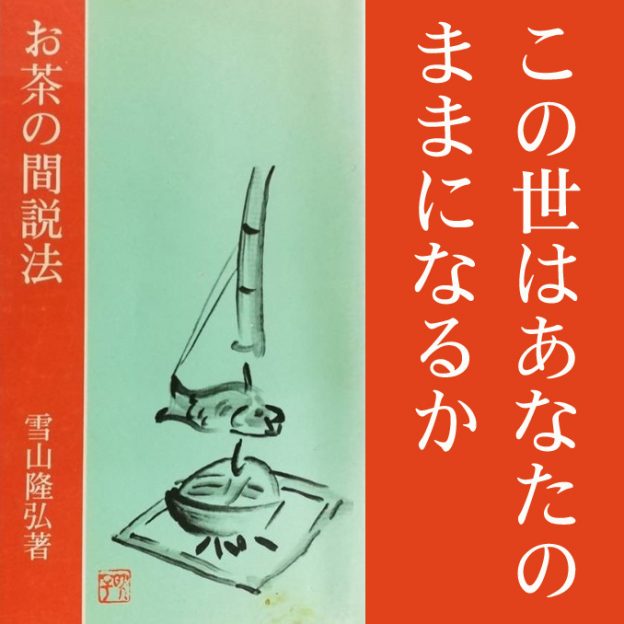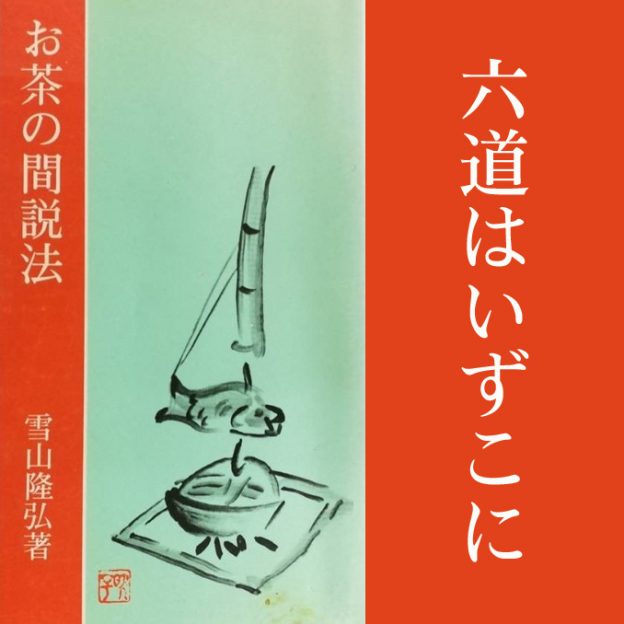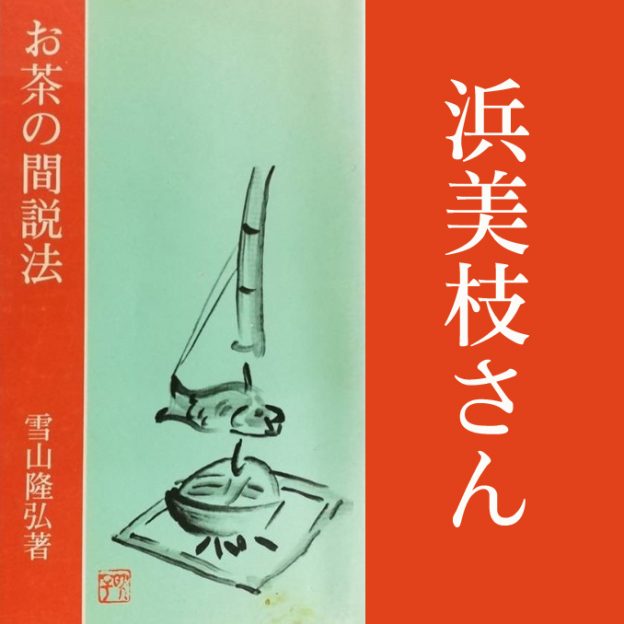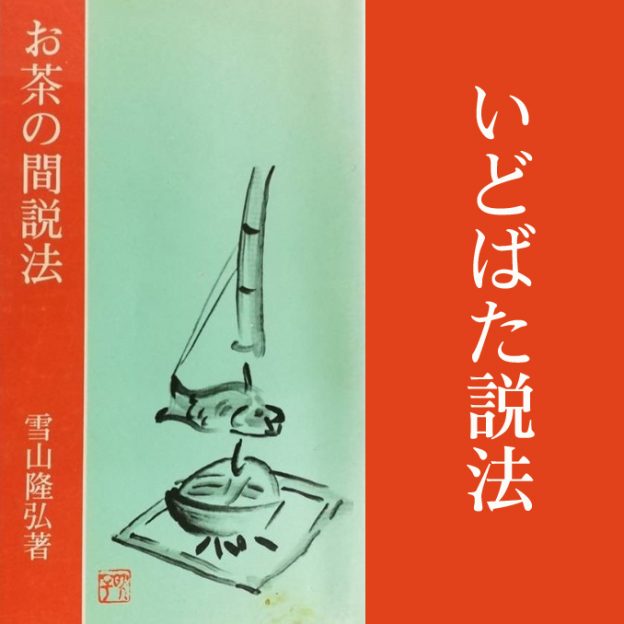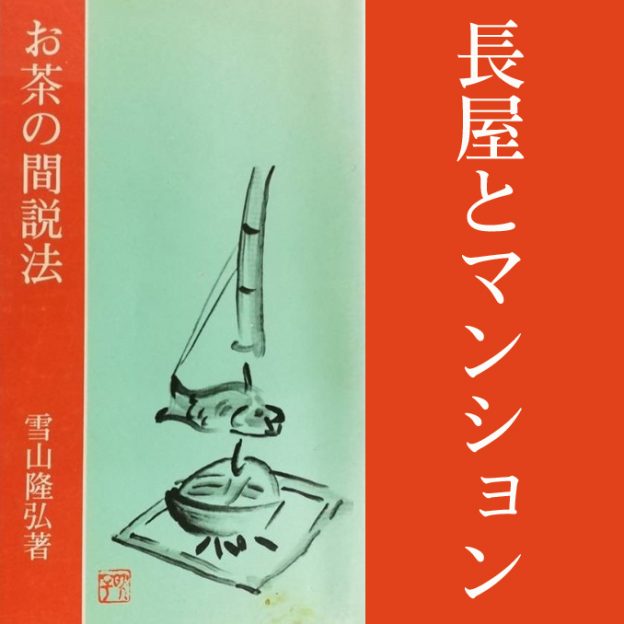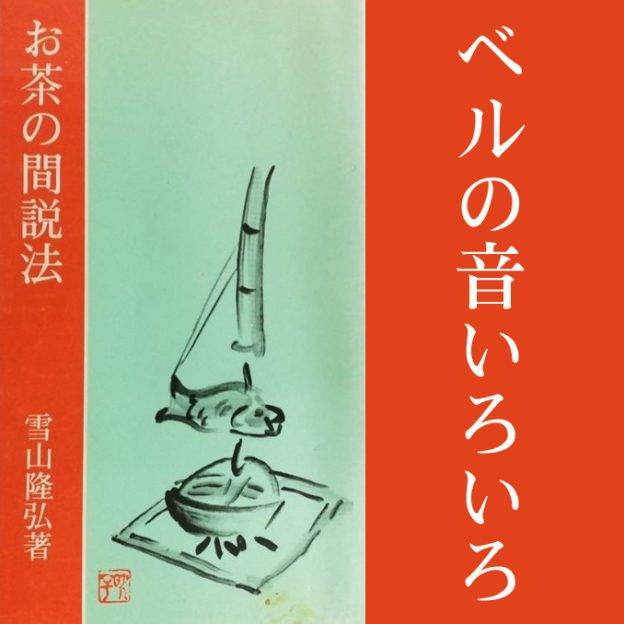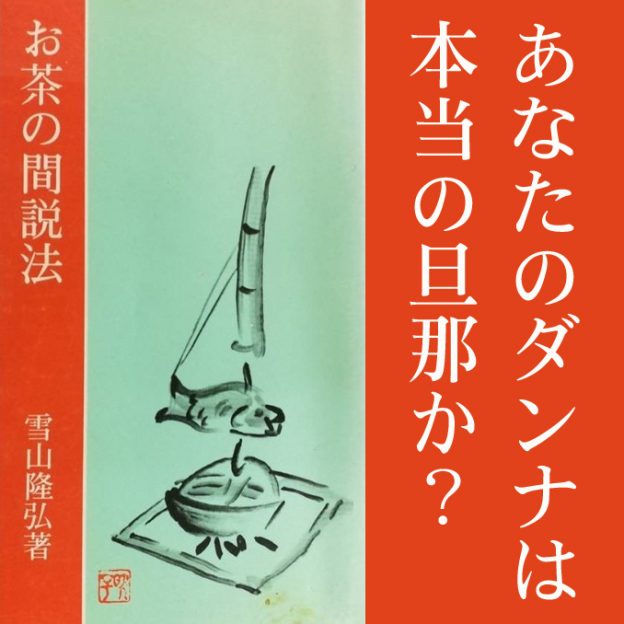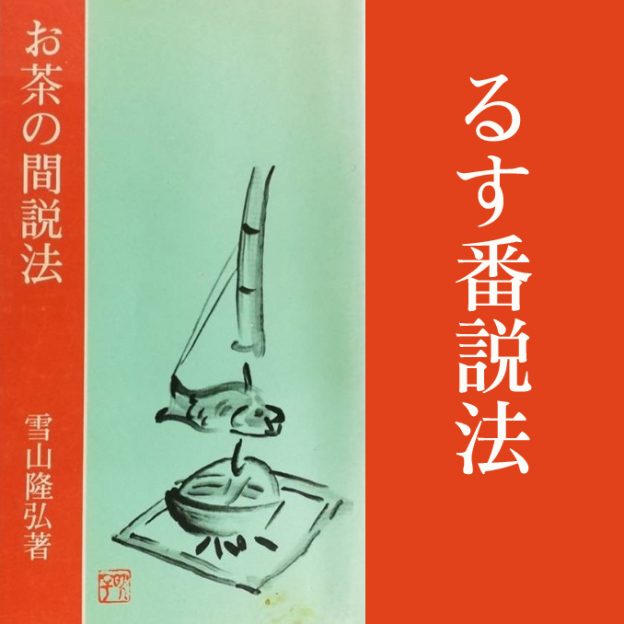Podcast: Play in new window | Download
Subscribe:
昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。末尾には、著者本人による録音音声があります。
ご主人は会社へ、お子さんは学校へー
いつものことだけれど、たいへんでしたね、けさも。でも、これからは、あなたの時間。だれにもじゃまをされない、ひとりっきりの留守番タイムのはじまりです。寝なおしますか?きのうのつづきのテレビを見ますか?さっそくラジオの伴奏で掃除洗たくですか?
オヤッ 素晴らしい。あなたは新聞を読んでいらっしゃる。そしていま、わたしとあなたはピッタリと視線が合ってしまった。これはたいへん。ムダ口たたいていないで、さっそく”るす番説法”をはじめることにいたしましょう。
時まさに敬老月間、ということで、けさはあなたにとっても身近な問題、お年寄りについて、わたしの感じていることを少しばかりー。
まず、この老人ということなんですが、「老」という字を調べてみると、背のまがった人がツエをついている姿、そこからこの字がうまれたんだそうですね。で、その意味はどうかと申しますと、年長者、おとろえた人、古い人、経験ある人、などとなる。
正直なところ、若い連中にとっては、これすべて気にさわることばかりですよね。おとろえた人ーということは、自分の20、30年後の鏡のようなものだから、使用前、使用後みたいな感じで、あーあ、わたしもこんなになってしまうのか、とタメ息の一つもつきたくなる。古い人ーということでいえば、若いものは新しがり屋ですからね、どうもしっくりこない。さらに、経験ある人ーということになれば、これはもうピターッと床に頭をつけて、聞かせていただくしかないのだけれど、素直にそうしているかといえば、なかなかそうはいかない。なにくそ負けるもんか、という心がムラムラとわいてきて、若さと新しさでもって、老いたるもの古いものを押さえつけてしまおうとする。
古い人、経験ある人というのは、自分一人で生きてきたのではなく、あらゆる人のおかげによって生かされてきたんだ、ということを知っている。
先日テレビで80歳を超える財界人、原安三郎さんがいっていました。「わたしがこうして長生きできるのも、親のおかげ、先祖のおかげ、みなさんのおかげだ」と。それに尺貫法で頑張った永六輔さんも「明治の人たちには、祈りと感謝の心がある。なのにボクたち、そのへんをチットモうけついでいないということに、トテモうしろめたさを感じる」といっていた。
1坪3.3平方メートルといい、1尺を30.3センチと換算しなければならない不自由さと同じように、ひょっとしたら、わたしたち、古くから語りつがれてきた”おかげさま”という心を”おカネさま”に換算してしまって、それでいま、心のサバクなどという不自由さにぶつかっているのではないでしょうか。これは尺貫法よりさらに根深くお年寄りの心を傷つけているようで、近頃のおばあちゃんやおじいちゃん、まるで元気がない。古くてよいこと、経験によって得たことの一かけらも口にすることができなくて、小さく小さくなっている。
がんばれ!おばあちゃん。老人の老は、背のまがった人がツエをついている姿だといったけれど、そのツエをムチに持ちかえて、若いものをしかっている姿―それが教育の「教」という字なんだ。もっと自信をもって、若いものを教えてほしい。ムチでビシビシしかってほしい。
そして、わたしたち若いものは、お年寄りのチエを、謙虚に聞く耳を持とうじゃないですか。そりゃあ気にさわることもたくさんあるかもしれないけれど、そこは思いやりと察し合い。もしいま聞いておかなかったら、大事なものを永久に失ってしまうことになるかもしれない。——年に一度の老人の日に、形ばかりの花を贈って、おじいさんおばあさんありがとうなんていっている自分を、深く反省しながら、こんなことを思うのです。
雪山隆弘
昭和15年生まれ。大阪・高槻市の利井常見寺の次男として生まれ、幼い時から演劇に熱中。昭和38年早稲田大学文学部演劇専修を卒業後、転じてサンケイ新聞の記者、夕刊フジの創刊メンバーに加わりジャーナリスト生活10年。されに転じて、昭和48年に僧侶(浄土真宗本願寺派)の資格を取得し翌年行信教校に学び、続いて伝道院。同年より本願寺布教使として教化活動に専念する。善巧寺では、児童劇団「雪ん子劇団」をはじめ永六輔氏を招いての「野休み落語会」など文化活動を積極的に行う。平成2年門徒会館・鐘楼建設、同年往生。
<-目次-「お茶の間説法」>
・お目覚め説法
・いい天気ってどんな空?
・カガミよかがみよ鏡サン
・心のファウンデーション
・決めた!はヤメタのはじまり
・だいどこ説法
・スプーンはおいしさを知らない
・ひとりいきいき
・いただきます、してますか?
・おかげさま?おカネさま?
・るす番説法
・あなたのダンナは本当の旦那か?
・ベルの音いろいろ
・長屋とマンション
・ひとりよりもふたり
・いどばた説法
・浜美枝さん
・六道はいずこに
・この世はあなたのままになるか
・天上界は二分半
・ようこそ、ようこそ
・居直るか、痛みを感じるか
・千々に乱れてグチばかり
・生きがいと死にがい
・名CMその後
・ストーブで心は暖まらない
・ハウツー説法
・お布施は出演料じゃない
・焼香は何のために
・仏だんの意義
・ありがとう、さようなら
・お茶の間説法
・焼きイモの味
・女のよりどころ
・男は富貴
・煩悩はいくつある
・チャンネル説法