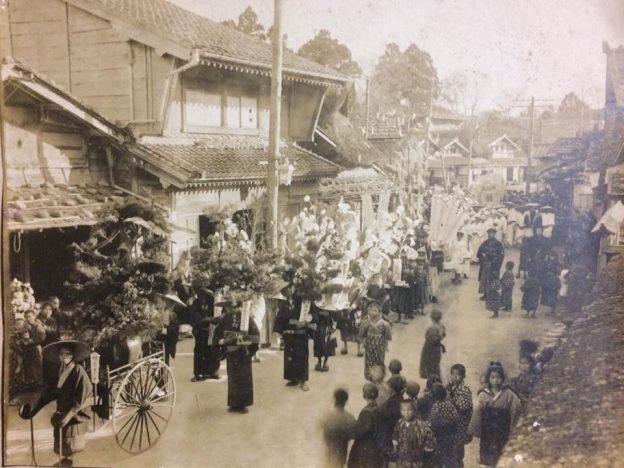本願寺の青少年育成を担当する部署に関わるようになり数年が経ちました。そこで頂いた学びのひとつを紹介します。
いのちは大切ですか?
精神科医の松本俊彦先生によると、中高生の約一割の子は自傷の経験があり、その中で96%は誰にも告げずにその行為に及ぶそうです。その多くは、家庭環境に問題があったり、学校でいじめを受けている場合があります。そのような子たちに、多数派に属する大人が「いのちの大切さ」を曖昧な表現で語っても、余計に自分自身を否定されたと受け取り、遠ざかっていくのかもしれません。
一割というのは他人事ではなく自分自身にも向けられることだと思います。私の心にも一割、縁に触れれば虚無感を持ったり自暴自棄になる心があります。そう考えると簡単に「いのちは大切」とは言えません。
鳩のいのちを救うために自ら痛みと苦しみを引き受け、自分のいのちを差し出したシビ王の話が思い出されます。他にも身を差し出す仏教説話はいくつもあり、それらは人を救うということがどれほどに重いことなのかということと同時に、いのちの大切さを知らない我が身を知らされます。
松本先生いわく、信頼できる大人になるためには、子どもが誤ちを犯した時にいきなり善悪の価値判断を決めつけないこと。そして、自分の手に負えないと思った時には、仲間や専門家に相談してみんなで支えることが大事だと言います。多数派が少数派を苦しめている現実に、目を反らさないようにしたいです。
雪山俊隆(寺報164号)