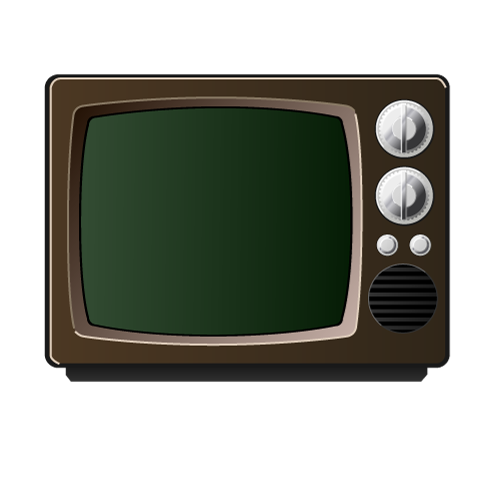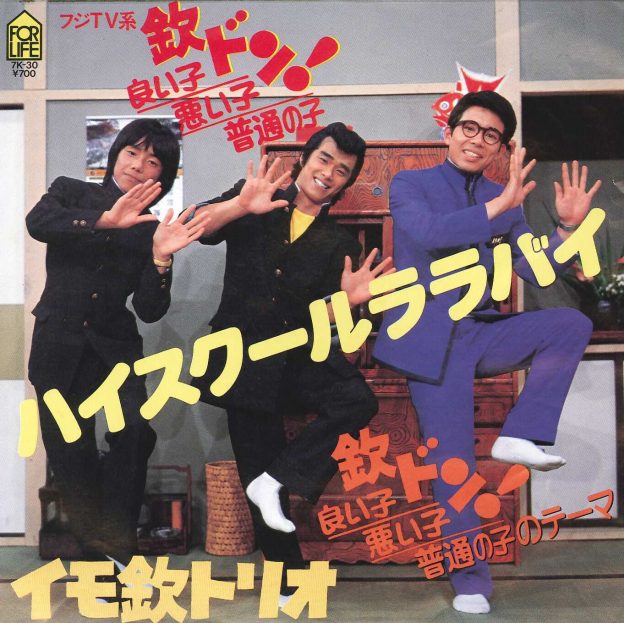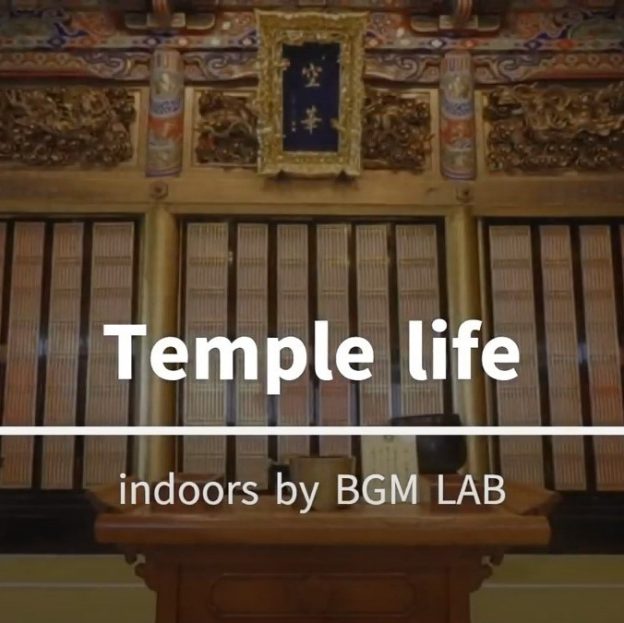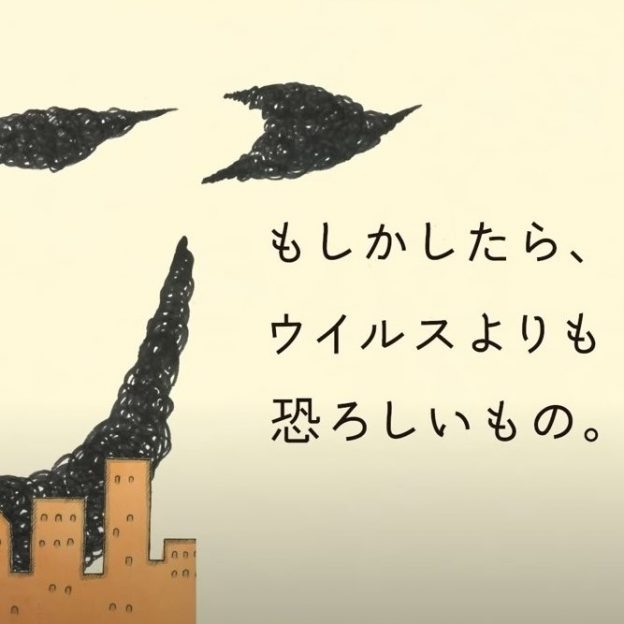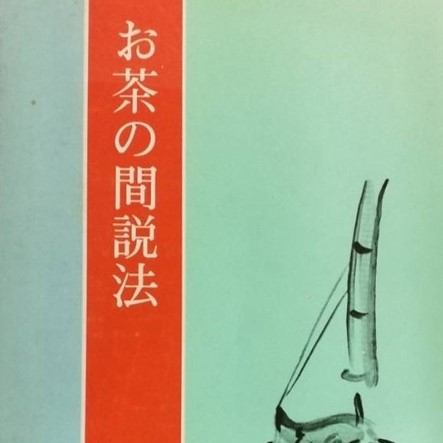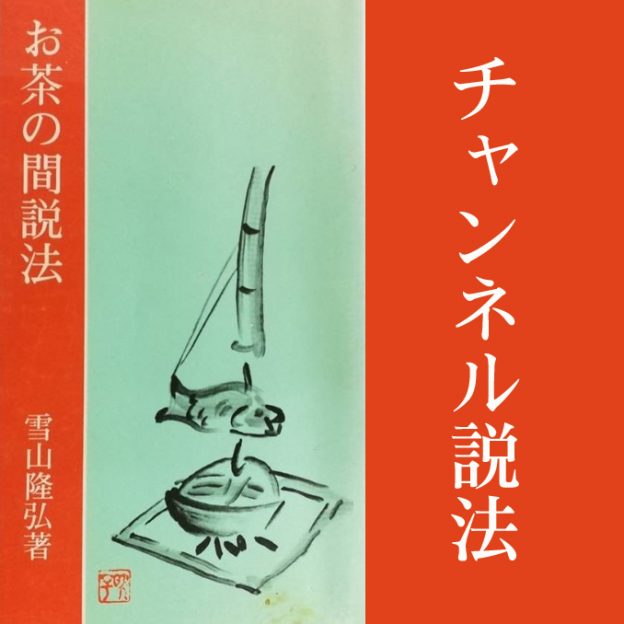Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: RSS
昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。
「コレッ!なにやってんのよ。さっさとしなきゃ、ダメでじゃないの」
あなたのこんなお説教を聞いて
(そうか、ボクは間違っていたんだな。それでお母さんは、ボクをしかって、正しい道を歩ませようとしているんだな。ああ、親なればこそだ。お母さん、ありがとう!)
などと、子供が思ったりするだろうか?
「いいかいキミ、僕はキミの為を思っていうんだよ。キミの将来を考えればこそ、こんなこともいわなきゃならないんだ」
こんな上役の説教を聞いて、素直に
(ハイ、反省します)
といえますか?
「ねえ、あなた、わかってちょうだい。わたし、あなたがイヤで、こんなこというんじゃないのよ。ただ、この家には二人の女がいて、これから仲良くやってゆかなきゃならないから、心を鬼にしていうんですよ」
姑さんのこんなお説教を聞いて、あなたは
(ああ、お母さん、ありがとう。わたしがいけなかったんだわ。鬼どころか、ほとけさまだわ!)
なんて思えますか?
お説教-かたくるしい教訓的なお話で、上のものが下のものへ、正しいものが間違っているものへ、お前はダメなんだ、ということを再確認させるようなところがあって、できることなら、そんな押しつけの説教は死ぬまで聞きたくない、というのが、私達の本音のようであります。つまり、人間はいつも自分を認めて生きている。自分に丸をつけて生きています。自分が上で他人が下と考える、これを「慢」といいます。その慢にもいろいろありまして、「やったア!勝った勝った」と、単純に有頂天になるのを「我勝慢」。「へー、あいつ、とうとう局長になったか。おや、こいつ校長か…ハハハ、こいつらみんな、オレの同級生だ!」ー同級生だからどうだって聞かれるととても困るんですが、とにかく、えらくなった人と、自分がどこかでつながっているということで自慢するのを「我等慢」といいます。そう、金田正一さんの口ぐせに、こんなのがありました。
「ハハ、大臣も女優さんも、ワタクシもメシ食って、出して、寝る、同じやねー!」
さて、三つ目の慢は、「我劣慢」
「困ったわぁ、どうしましょ。わたし、奥さんに負けちゃった。ほーんと、かなわないわ」なんて、負けた負けたといってるけど、本心、ちっとも負けたと思ってない。ほんの一部はあなたに劣っているけれど、あとの大部分は、わたしの方が上、と自慢するのを我劣、あるいは「卑下慢」というんだそうです。
ところで、こんなエグイもの、だれが持っているのかと申しますと、生きとし生きるものみなすべて、だと、仏様がおっしゃる。あなたも、わたしも、煩悩具足であります。具足というのは、一つとして欠かさずに持っているということでありますが、これに気がつかないのがあわれ凡夫のわたしなんです。
で、つまりは、私達は他人に「お前はペケだ」なんていわれるのは大嫌いなのでありますが、逆にお説教する方はというと、これはもう大好きで、そういう人間は、私をふくめてあなたのまわりにもゴマンといるんじゃないですか。いや、ひょっとしたら、あなたもふくめてかな?
「お茶の間説法」第一巻はこちらからどうぞ。
>> http://www.zengyou.net/?p=5702