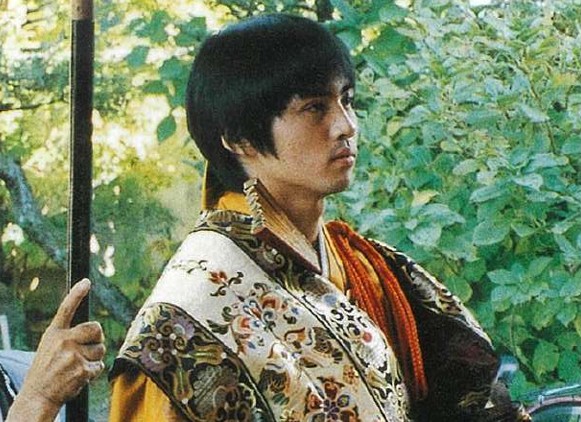年末年始は宗教行事が続きます。まずは、クリスマス。それからお寺で除夜の鐘、神社参り。この三つを一週間の間に全部参加するというのは、日本の他にはないと思います。今回は、せっかくなので、信仰ということについて少しお話させてもらいます。
宗教とか、信仰というと、みなさんはどんなイメージを持っているのでしょうか。なんか怪しくて、ダークなイメージですか?身近に感じられない人も多いと思います。でも、じつは身の回りにたくさん溢れているんですね。例えば音楽。海外のミュージシャンの中には信仰を歌った歌が多くあります。もともと、音楽、歌で表現するというのは、宗教からはじまったものがたくさんありました。ゴスペルというのは、キリスト教から生まれたものです。レゲエ、あれはジャマイカのラスタファリズムという信仰から生まれたものでした。テレビを見ていても、いろんなものが見えてきますね。イスラムの方が礼拝している姿。オリンピック選手が大地にひざまずいて十字を切る姿。もっと身近なところでは、家でばあちゃんが仏壇に手を合わす姿。それぞれに対象は違いますが、自分を超えたはたらきへの感謝をあらわします。ありがとう、の想いをカタチにしたものですね。カタチは心を育てます。
今は、科学的なものの見方と、お金で世の中がまわっていますから、「自分を超えた存在」なんていうと、なんじゃそりゃ?と思う人も多いと思いますが、これもちょっと考えてみれば、目には見えないはたらきって無数にありますね。たとえば、空気。空気がなければぼくらは生きていけません。太陽も地球も、水も生き物もそうですね。ぼくらは毎日生き物のいのちをもらいながら生きていて、そのおかげで体の機能も働いています。体の中も自分で動かしているわけじゃないですね。心臓をイチニイチニと動かしている人はいません。最も今はペースメーカーってのがあって、化学技術の力も入っていますが、でも全体からみればほんの一部でしょう。体のひとつひとつの細胞も、生まれては死んで生まれては死んでと繰り返しているそうです。でも、そういうことにぼくらは意識せず毎日を過しています。こういうものへの感謝、必要ないでしょうか。
ラジオ番組「ゆるりな時間」より