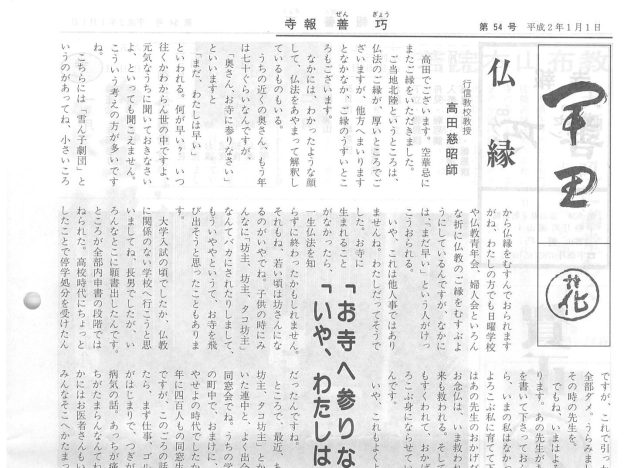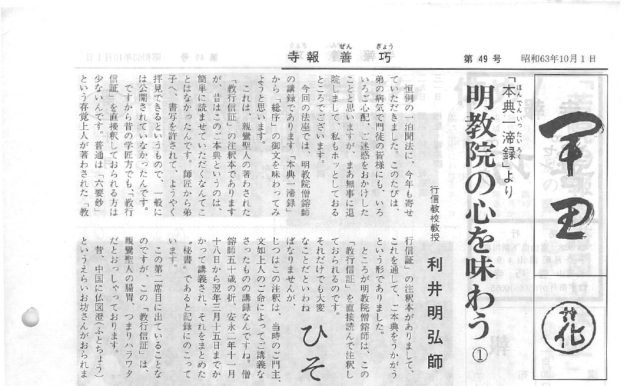このテキストは、昭和63年、空華忌の法話を一部抜粋して寺報(47号、48号)に掲載したものです。
自はをのずからといふ 然はしからしむよいふ
行信教校教授 高田 慈昭師
自然合成 自然快楽
親鸞聖人が、他力ということを深く味われましたお言葉の中に「自然法爾(じねんほうに)」というのがございます。末灯鈔というお聖教の中に出てくるのですが、この言葉は仏教の深い意味をあらわしているものなのでございます。
ところで、この夏のことなんですが、ベルギーの青い目のお坊さんがおられまして、この方はそのベルギーのアントワープという町の大学の先生もなさっているのですが、アドリアン・ぺ―ルという方なんです。
このペールさんは、仏教に帰依し、浄土真宗に帰依し、京都のご本山で得度もされまして、今、ヨーロッパにお念仏の教えを広めて下さっているのであります。小さいときはキリスト教の聖歌隊のメンバーだったそうです。でも今は、私の救われてゆく道はこれだと、心の底からよろこんでいらっしゃるんです。そう、ベルギーには今、ペールさんのお寺があるんですよ。寺号は「慈光寺」というんですが、このお寺の名は私の寺の名と同じなんで、何かとても親しみ深く感じるのです。
このペール博士がね、親鸞聖人の教えは「自然法爾」という、本来、ありのままの凡夫が、凡夫のままに救われてゆく、そこには阿弥陀様の絶対的なお慈悲の世界が開かれ、その世界に招かれてゆく…ということを心からよろばれておるのでございます。
私はこの夏、ペールさんと通訳を入れてお話をしたのでありますが、その時にもこの「自然法爾」のおいわれが、人々が救われてゆく無理のない真実の法だとおっしゃっていたのであります。
この「自然法爾」という味わいは、西欧人の考え方からはなかなか出てこないものなんですが、それを適確に押さえていらっしゃるところにたいへん感心させられました。
さて、この、自然法爾という言葉でありますが、本来は仏教全般の言葉でして、禅宗でも使いまして「自然のほうは、つくる人があることもなく、つくらないこともない。法爾自然、生死自然、因果自然…」などと申します。
で、私達の経典、仏説無量寿経にも、自然という言葉が、五十五ヵ所も出てまいります。うかうかと唱えていると気づきませんが、親鸞聖人はこれを本当に深く見つめられたんですね。
自然在身、自然合成、自然快楽、自然飽足、自然化生、無為自然…
また、観無量寿経の中にも、
自然増進、自然在中、自然化成
などと六ヵ所、そして阿弥陀経には
皆自然生念佛念法念僧之心
と、一ヵ所ですが出てきます。
さらに、宗祖のお正信偈の中にも「自然即時入必定」とありますね。
それで、この自然という言葉を浄土真宗では、特に阿弥陀如来の本願力の自然、願力自然と使うのであります。
阿弥陀如来の本願力が、自ら然しむる、こちらには何一つ計らう余地はない、如来の計らい一つによって、あるがままに抱かれて救われてゆくのである、と味わうのであります。
親鸞聖人が晩年に、京都の善本院というお寺で、弟ぎみの尋有僧都に、仏教で自然法爾ということがあるぞ、というって、願力自然ということについてご法話をなさったんですが、これが、自然法爾章として、末灯鈔にのこされているのであります。
自然といふは、自はをのづからといふ、行者のはからひにあらず、然とうふ、しかしむといふことばなり。しからしむといふは行者のはからひにあらず、如来のちかひにてあるがゆへに法爾といふ。法爾といふは、この如来の御ちかひなるがゆへにしからしむるを法爾といふなり。法爾はこの御ちかひなりけるゆへに、をよそ行者のはからひのなきをもて、この法の徳のゆへにしからしむるといふなり。すべてひとのはじめてはからはざるなり。このゆへに義なきえを義とすとしるべしとなり。自然といふは、もとよりしからしむるといふことばなり。弥陀佛の御ちかひのもとより行者のはからひにあらずして、南無阿弥陀佛とたのませたまひてむかへんと、はからはせたまひたるによりて、行者のよからんとも、あしからんともおもはぬを、自然とはまふすぞとききてさぶらふ。……
とこのように、じつに味わい深い、他力のおみのりをおのべになっておられるのであります。
ところで、この他力といいますと、人の力をあてにするというように間違って使う人が多いんです。野球でも何でも、他力本願で優勝なんて言う人がいますな。困ったものです。優勝したのは他力でも何でもない。実力なんですがね。
仏教では他力とか自力というのは、仏さまのおさとりに向かうときに言う言葉なんで、人間生活の上で自力他力は言わないんです。それを日常生活でこういう仏教の尊い言葉を使ってしまうから、本当の心をみな忘れてしまう。他力というのは人間の力ではないんです。仏さまの力、阿弥陀如来の本願力なんですよ。凡夫が仏になるのに如来の本願力一つによって救われてゆく…それはこちらが願う前に、仏さまのほうから願われてある、大きな限りないお慈悲の世界、それをあらわすのであります。
行者のはからいにあらず
ところで、ふつうはこの「自然」を「しぜん」と読みますね。仏教では「じねん」といいます。「しぜん」というとなんか科学的な感じがしますけど「じねん」というと、何かこうあたたかい感じがしますね。
で、ここで少し、その「しぜん」と「じねん」の共通点を上げてみようと思うんですが、まず第一に「しぜん」は人間の手を加えないことがあげられます。人工を借りないのであります。まあ、これが本来の姿というものでしょう。それと同じように阿弥陀如来の本願も、南無阿弥陀佛のお名号をもって、われらを救いたもうがゆえにこの本願を信じて一声にも念仏を申さば、必ず仏のおたすけにあずかるなり、これ法爾道理なるべし、と法然上人もおっしゃっています。これこそ、自ら然らしめたまう真実のおみのりなのだというわけです。行者のはからいにあらずということなんですね。
第二に、しぜん、じねん、ともに因果の秩序、法則があります。自然界には原因と結果の道理が貫かれてあります。花は咲くべくして咲き、散るべくして散ってゆくものですね。ウリのつるにはナスビはならんということですね。
仏法というものもその通り。おしゃかさまがお出ましになって、因果の道理を見抜かれた。これはおしゃかさまがお出ましになる前からちゃんとあった法則です。
今、阿弥陀如来のご本願もそうでありまして、私達を救って下さる、救いの因果と、救われる側の私達の因果がございます。
如来の救いの因果とは、法蔵菩薩の願行が「因」となり、正覚の阿弥陀如来が光明と名号となって私のもとに届いてくださる、これが「果」であります。
この如来の因果が、私に届いて私の信心の「因」と、往生成仏の「果」となって下さるのであります。如来さまのお救いというのは神秘の魔術ではなくて、厳然たる因果の道理によって、間違いなく、救いの法が仕上がり、その法によって間違いなく救われてゆく法が、私どもの上に届いておって下さる。それがお念仏なんです。そこに人間のはからいを越えた、如来のはからいとしての真実の大悲のはたらきが、今、私どもの一人一人の煩悩を照らして、その全体に南無阿弥陀佛の功徳を注いで救って下さる、そこに因果の道理が成立し、自ら、然しむるのであります。
自然法爾を味わう②
はからいなしすべて如来の…
親鸞聖人の末灯鈔のお言葉をみますと、まず自然という言葉のご解釈がでてきます。
自というのは自ずから、行者のはからいにあらず、然というのは然らしむる、行者のはからいにあらずという」どちらも行者のはからいにあらずという風にのべられています。法爾というのは「如来の御誓いなるが故に然らしむるをいう
とのべられています。
この自然という文字、自という文字はみずからとおのずからという二通りの読み方があるわけですが、みずからというときは自分自身ということで親鸞聖人は、五会法事賛の観音勢至自来迎、観音菩薩と勢至菩薩が、自ら来迎したもうという言葉をご解釈され、二菩薩みずから私共、念仏者をお迎えとって下さるという云い方をされています。ところがその後に聖人は、また自というは自ずからというとご解釈され、おのずからというときには自ということである。阿弥陀如来のお救いが行者のはからいをはなれて、向かうからしからしめて下さるという働きであるという風に他力ということをあらわされています。今は自というのはみずからという意味ではなしにおのずからという意味である。おのずからは何故、行者のはからいにあらずというのかといいますと、自という字、これは「より」という字でもあります。今はあまり使いませんが〇年〇月〇日より〇日にいたる、というときにこの字を使っています。ものがはじまるもとということです。又、「より」というのは「従」、こちらが動かなくても向こうから動かん私を抱きとって下さる。如来さまの方から全くはかろうて下さるから、こちらからは毛すじほどもはからう余地がない、こちらから動いてゆくことではありませんから、行者のはからいにあらずというわけです。
太陽というのは向こうにあるけれども、光はここにとどいている。そして私達を照らし、私達の暗を破り、又、育ててくださる。向うかから働きでじっとしているままが、こちらは光をいっぱいあびている。向うから近づいて、この煩悩の世界にいきいきと働いて、この私をおさめとって下さる。こちらの方は素直にこれに従うよりほかはない、大きなめぐみであるなァと仰いでゆく他はない。だから行者のはからいにあらずというのであります。向うからの働きでありますから、然という字は、またこれ然らしむるといいます。
親鸞聖人は必ずという字を必得住生とおっしゃっています。善導大師は、南無阿弥陀仏でどうして往生できるか、それは南無阿弥陀仏の中に、願と行がちゃんとこもっておる。仏のさとりにいたる願と、仏のさとりにいたる行が、全部、南無阿弥陀仏におさまっておるから、どんな凡夫でも、南無阿弥陀仏ひとつで必ず往生を得るとおしゃった。
善導大師のころには、お念仏の教えを知らないで、凡夫の唱える位のお念仏で、どうして仏になれるのかと、念仏の教えをけなした人達が多かった。そこで善導大師が憤慨と立ち上がりましてね。そうではない、お念仏一つによって凡夫が救われてゆくのである。そのわけを言うなら、南無というは帰命である。またこれ発願廻向の義なり、如来の願いが私の所にとどいて、私が仏になる願がちゃんとそなえられている。しかも、阿弥陀仏は即ち行といえり、阿弥陀仏という中に、この凡夫を仏にする行のありだけがこもっていて全部私のところに、信となり、念仏となって浄土へむかわしめてくださる大きな働きがある。
お寺の垂れ幕にありましたな、「法体大行」。如来の行が私の行になって下さっておる、如来さまが苦労して仕上げて下さった行のありたけが、私の信となり、行となって下さる。信心ということは、如来の大願大行が私のところへとどいて下さったということです。
浄土真宗に行があるかと云われた時、私達は堂々と大願大行という行があります。それが私の体を通して出ておってくださる南無阿弥陀仏の一声一声の無上の功徳が躍動しているお念仏なんだということを、私達は、親鸞聖人の教えを通して味わっているんです。
法然上人は選択本願のお念仏とおっしゃって居ます。そのようにお念仏で凡夫が間違いなく救われてゆくということを、はじめて道理をもって示されたのが善導大師。必ず往生をうるということが如来の自然法爾であるから、その道を歩む人間になさしめたもうのであります。
庄松さんでしたかなあ。友達が病気で寝ていました。病気をすると心が不安で、ひょっとして悪くなって死ぬんじゃないか庄松さんに仏法のお話をしてほしいというので、その友達の家へ見舞にゆきました。そしたら庄松さん、病人に話でもするかと思うと何もしないで、隣の部屋のお仏壇の前に座って、おあかりつけておつとめをするんです。長い長いおつとめをゆっくりゆっくりしておりまして、仲々おわらない、病人がいらいらしてお前をよんだのはおつとめをしてくれということではない、早く私の枕元へきて早くお話をしてくれというと、「ここに大悲の如来さまがお立ちになってるじゃないか、この如来さまが正覚を成就して私のところへ南無阿弥陀仏ときて下さっておるのに何が不足かいおらみたいもんの話きいたって何にならあ、願力自然の働きで私のところへ南無阿弥陀仏となってだきしめておってくださる親さまが、ちゃんとおら達迎えになるのに、何が不足かい」と云うとナモアミダブツとお念仏しながら帰っていったんです。
この病人の友達が後から考えてなるほどなァとわかったんですね。何かありがたい心になろう、自分の不安を破ろうと思って、それに、はからいをした。人生の矛盾や、人間の不安は人間の力で破ることはできません。くよくよした妄念や不安が最後までなくならないのが本当の姿です。しかしその不安のままが、如来様の確かな法の中にそのままだかれて救われておるところに、ゆるぎない安心が与えられておるのです。
おのずから然らしむるということの言葉を私達は本当にかみしめて味わわしていただいたら「このままでよかったなァ」「このままが、本当に自由な大きなめぐみの中にいだかれておりましたなァ」と、心の底から晴れ晴れと念仏を申すよりほかにないのであります。